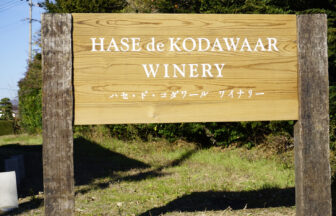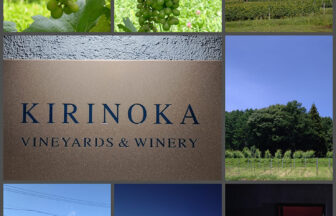今回紹介するのは、栃木県栃木市大平町出身の岩﨑元気さんが手がける、ぶどう栽培とワイン造りについて。栃木市大平町は食用ぶどうの産地として歴史があり、岩﨑さんの実家も生食用ぶどうを栽培している農家だ。
大学生の時にワインと出会って深い魅力を知った岩﨑さんは、ワインへの情熱を絶やすことなく燃やし続けてきた。就職先はワイン輸入業者で、その後フランスに留学してワインについて専門的に学んだ。「フランス国家公認醸造士・エノログ」の資格を取得した後、2024年に帰国し、念願だった地元でのぶどう栽培とワイン醸造をスタートさせたところだ。現在は、マスカット・ベリーAを主体としたワイン造りに取り組んでいる。
岩﨑さんのルーツやぶどう栽培、ワイン造りへのこだわりなどについて、様々なお話を伺うことができた。栃木を盛り上げるために岩﨑さんが目指す未来を共に見ていこう。
『ワインとの出会いから、現在までの歩み』
まずはじめに、岩﨑さんとワインの出会いから、ワイン造りを始めるまでの歩みを振り返ってみたい。
ワインの魅力に気づいたのは大学生になってからだったという岩﨑さんは、どのような思いでワイン造りを目指し、どのような経験をしてきたのだろうか。
▶︎岩﨑さんとワインの出会い
岩﨑さんが初めて魅力を感じたワインは、大学の友人と飲んだ南アフリカのカベルネ・ソーヴィニヨンだった。美味しいワインの存在を知ったことで、ワインの魅力にどんどんのめり込んでいったという。近くの酒屋が開催していたワイン会に積極的に参加するようになり、フランスワインの銘醸地であるブルゴーニュやアルザスのワインとも出会った。
ワインのことをもっと知りたいと願った岩﨑さん。大学卒業後は、ワインショップとワインの卸売をおこなっている企業「エノテカ株式会社」に入社。東京勤務を経て軽井沢に転勤した先で、さらにワインの世界に深く足を踏み入れていった。
「軽井沢で勤務している期間にも、ワインにまつわるさまざまな出会いがありました。農家さん主催のワイン会に参加したり、長野県東御市の醸造家さんと交流したりと、ワイン三昧の日々でしたね」。
いつしか、岩﨑さんには新たに、ワイン造りに対する興味が芽生えてきた。幸いにも、岩﨑さんの実家はぶどう農家だ。いつか地元に帰って、ぶどう栽培をしながらワインを造りたい。そんな未来を想像するのは難しいことではなかった。そこで、まずは本格的にワイン造りを学ぶことを決意し、フランスに渡ることにしたのだ。
▶︎フランスでワイン造りを学ぶ
フランスでのワイン造りの修行と勉強は、トータル7年にも及んだ。
「はじめの3年は労働者として働いていました。また、フランス・ブルゴーニュ地方のワイン産地であるサン=ロマンの『ドメーヌ・ド・シャソルネイ』や、ジュヴレ=シャンベルタンの『アルマン・ルソー』でも経験を積みました」。
その後、シャブリに移って2年間働き、技術研鑽に励んだ。がむしゃらに取り組む中で、岩﨑さんは次第に、より科学的・理論的にワイン造りを学びたいという考えを持つようになった。
「栽培をしていると、数々の疑問が生まれます。それぞれの作業をする理由を突き詰めて考えるためには、科学的な知識が必要でした。そこで、専門的に栽培と醸造を学べる学校に通うことを決めたのです」。
2020年にボーヌに引っ越した岩﨑さんは、「プリューレ・ロック」で働きながら、ボーヌ農業促進・職業訓練センター(CFPPA)に通った。続いて、ブルゴーニュ大学3年次(学士・ブドウ学)に編入。ブルゴーニュ大学醸造学修士課程で「フランス国家公認醸造士(エノログ・醸造学修士)」を修了した。そして2024年、ついに帰国の途についたのだ。
「フランス人でも入学が大変な学校で学び、名門ワイナリー『アンヌ・グロ』や『コント・ラフォン』などでの研修など、非常に貴重な経験を積むこともできました」。
▶︎フランスでの経験を日本で生かす
フランスで学んだ岩﨑さんには、そのままフランスに残ってワイン造りに携わる選択肢もあったはずだ。なぜ日本に戻ってワイン造りをすることにしたのだろうか。
「せっかく貴重な経験ができたのだから、自分にしかできないことに取り組みたいと考えました。フランスで活躍している日本人の醸造家は、すでにたくさんいらっしゃいます。社会のために自分ができることは何かと考えた時に、『フランスでの経験を日本ワインのために活用する』ことが一番大きなインパクトになるだろうと思ったのです」。
日本国内ではワイナリー数は激増しているものの、「日本ワイン業界」自体はまだ発展途上だ。例えば、フランスにおいては日本ワインの知名度は無いに等しい。フランスに輸出されている日本ワインは、なんと年間3,000本未満なのだとか。
「日本でワイン造りをする以上、将来的にはフランスにも輸出したいと考えました。そのための土台づくりとして、まずは日本ワインを知ってもらう場をつくったのです。2023年11月に『サロン・デ・ヴァン・ジャポネ』という日本ワイン専門の試飲会をフランスで開催しました」。
2025年現在、岩﨑さんは日本でぶどう栽培をしながら、委託醸造でワインを造っている。また、自社ワイナリーの設立に向けて着実に歩みを進めている最中だ。活動拠点は、出身地である栃木県栃木市大平町。なるべく早く自分の醸造所を持ちたいと話してくれた岩﨑さんの取り組みを紹介していこう。
『マスカット・ベリーAで、世界に誇れるワインを』
岩﨑さんが栃木市大平町で栽培しているのは、マスカット・ベリーA。日本でワイン造りをすると決めたときから、メイン品種はマスカット・ベリーAに決めていたという。
岩﨑さんが考えるマスカット・ベリーAの魅力と特徴、ぶどう栽培におけるこだわりを聞いた。
▶︎マスカット・ベリーAの魅力
「マスカット・ベリーAは、表現に幅が出るところが面白いぶどうです。赤ワインだけではなく、スパークリングワインやロゼワインにも使えます。また、同じロゼワインでも、白に近いものからピンク色が強いものまで造り分けられる点も貴重ですね」。
マスカット・ベリーAは、赤ワインにおいてもさまざまな表現が可能だ。すっきりした味わいや樽熟成した厚みのある風味、果実のボリューム感まで造り分けられる。醸造する際には除梗してもよいし、全房発酵もできる。マスカット・ベリーAのワインだけで飲み比べのワイン会ができるくらいなのだと、岩﨑さんは本当に楽しそうに話す。
マスカット・ベリーAにこだわる理由は、その他にも3つある。ひとつ目は、フランスでの受けがよいことだ。マスカット・ベリーAは、フランスのメジャー品種であるピノ・ノワールやガメイなどと近い香りの要素を持っており、口当たりもよい。フランスでおこなった試飲会の様子を見ても、マスカット・ベリーAの反応は特に上々だったという。
ふたつ目は、テロワールを表現しやすいぶどうだという点だ。マスカット・ベリーAは日本各地で栽培されているが、例えば山形、山梨、九州産のものでは全て味わいが異なる。地元・栃木の魅力を世界に発信することを目指しているため、土地の味わいをダイレクトに表現できるマスカット・ベリーAは、栃木の魅力をアピールできる品種だ。
3つ目は、栃木市大平町での栽培実績がある点だ。すでにおいしいマスカット・ベリーAが栽培されているということは、栃木の気候に合っているからだろう。品種のポテンシャルを発揮できる環境が整っていることは、大きなアドバンテージだと言える。

▶︎栃木市大平町のマスカット・ベリーA
岩﨑さんの実家は生食用ぶどうを栽培している農家で、1.6haほどの畑を保有している。しかし、マスカット・ベリーAの栽培量自体は少ない。
「周辺のぶどう農家と同様、高値で売れる巨峰やシャインマスカットを主に栽培しています。マスカット・ベリーAの栽培量は減少の一途を辿っていて原料の確保が急務になっているため、今後は畑の拡張が課題です」。
そのため、岩﨑さんは自分が管理するマスカット・ベリーA専用の畑を新たに取得する必要があった。当初は難航することを予測していたというが、以外にもスムーズに畑の取得が進んだという。
「非常にありがたいことに、地元に戻ってすぐに畑を借りることができました。高齢で離農する農家さんが声をかけてくださったのです。メディアにも積極的に出ている若い人材であるということもよかったのかもしれません」。
地域の産業を活性化させるために、今後も栽培面積をどんどん増やしていきたいと意気込む岩﨑さん。
「私が目指すのは、ただワインを造ることではなく、栃木市大平町を盛り上げることです。畑を拡大しても私ひとりでは管理しきれないため、協力してくれる人をどんどん増やして、規模を大きくしていきたいですね」。

▶︎栃木市大平町のテロワール
続いては、栃木市大平町のテロワールに注目してみよう。一帯は関東平野と丘陵地の境目に位置し、北東西を丘に囲まれている環境だ。岩﨑さんが管理する畑は晃石山(てるいしさん)の南斜面にある。
「三方を丘や山に囲まれていることで、雲から守られています。栃木市の中ではスポット的に降水量が少ない、特殊なエリアですね」。
また、昼夜の寒暖差が大きい点も、良質なぶどうの生育にとってプラスになる。晃石山から涼しい風が吹き下ろすため、夜温が下がりやすいのだ。
「栃木県は暑い場所だと考えられがちですが、いわゆる『メゾクリマ』に目を向けると、必ずしもそうではないのです。栃木市大平町はぶどう栽培に適した地域ですよ」。
岩﨑さんの畑は晃石山由来の岩砂と粘土質がベースになっている土壌だ。岩粒が多いため、水はけは良好。栃木市大平町で育つぶどうは、フレッシュな味わいになるのが特徴だ。糖度が上がりやすい一方で酸もある程度残るため、複雑味を有した凝縮感のあるワインが生まれる。

▶︎副梢栽培の導入を検討
岩﨑さんが目指すのは、複雑で深みがあり、しっかりと厚みのある味わいのワイン。栃木市大平町のぶどうは、複雑味と深みはクリア出来ているが、厚みはもう少し欲しいところだ。栽培技術でカバーする必要があるため、3つの試みを検討している。
ひとつは、補助品種を入れること。気候変動による気温上昇は、葡萄の色づきや糖度を不安定にする。今後も気温上昇の傾向は続くと見られているため、足りない要素は別の品種で補おうと考えている。
「マスカット・ベリーAに10%程度のプティ・マンサンをブレンドできれば、一定の糖と酸を与えられます。2025年からプティ・マンサンを栽培するため、準備をすすめているところです」。
ふたつ目の工夫は「副梢栽培」をおこなうこと。副梢栽培とは、新梢の先端をあえて切って脇芽を生やし、伸びた脇芽にできたぶどうを収穫する栽培方法だ。後から伸びてきた芽にぶどうができるため、収穫時期を後ろ倒しにできる。発表されている論文によると、色づきがよくなり糖度が上がるうえ、酸が上昇することも確認されているそうだ。
「導入のメリットが多い副梢栽培を試さない手はありませんが、栽培中のすべてのぶどうをいきなり副梢栽培に切り替えることはできません。すでに栽培中のぶどうはそのままの仕立て方を継続し、これから新しく植えるぶどうを副梢栽培で管理しようと考えています」。
副梢栽培を導入する際には、ぶどうが受けるダメージを最小限に考慮したいと話してくれた岩﨑さん。新梢をあえて切って脇芽を生やすことで、ぶどうは生育に余分なエネルギーを使うことになる。そのため、成木になるのを待ってから副梢栽培を導入し、さらに畑ごとに交代で実施する予定だという。
『厚みあるマスカット・ベリーAのワインを生み出す』
岩﨑さんが目指すのは、長期熟成も可能な複雑味と深みのあるワイン。モデルにしているのは、ブルゴーニュのワインだという。ブルゴーニュでの醸造経験やワインの研究が、岩﨑さんの技術と知識を形作っているからだ。
ここからは、目指すワインを実現するために岩﨑さんがおこなっている工夫と試み、こだわりについて紹介していこう。
▶︎マスカット・ベリーAの可能性を引き出す「全房発酵」
試行錯誤を繰り返しながら、少しずつマスカット・ベリーAのワインのレベルを上げている岩﨑さん。取り組みのひとつに、「全房発酵」に関する試行錯誤がある。
全房発酵とは、ぶどうの茎を取り外す「除梗」をおこなわず、房に梗がついたままで丸ごと発酵させるスタイルを言う。全房発酵することで、茎が持つタンニンや風味がワインに付与され、厚みや複雑味のある味わいになるのだ。
「マスカット・ベリーAは全房発酵が合っている品種だろうと考えていました。予想は当たっていましたが、実際やってみると調整が必要な点もありましたね。マスカット・ベリーAは、ある程度実を潰さないと成分が溶け出しにくいことがわかったのです。茎を付けてそのままの状態で漬け込んでも、色素がうまく抽出できませんでした」。
そこで岩﨑さんが考えたのは、果実を除梗破砕したうえで、後から茎を足して発酵させる方法だ。このやり方であれば、マスカット・ベリーAの皮が持つ色や成分を引き出しつつ、茎由来の香りや味わいも加えることができる。

▶︎マセラシオンの期間を試行錯誤
マスカット・ベリーAの醸造では、もうひとつ重要なポイントがある。醗酵中のワインに果皮を漬け込む工程である「マセラシオン」のベストな期間を見極めることだ。特に醸し後半の温度と期間が決め手になるという。
「マセラシオンについても試行錯誤が必要でした。例えば、ピノ・ノワールの場合なら、しっかりとした味わいのワインにしたければ、マセラシオンの期間を延ばして30度近くまで温めます。皮からタンニンがしっかりと溶け出して、色が濃く厚みある味わいにするためです。その技術をマスカット・ベリーAにも使おうと思ったのですが、試してみたところ、マスカット・ベリーAには合わないことがわかりました」。
どうやらマスカット・ベリーAでは、マセラシオン期間を短くしたほうがよさそうだった。その理由のひとつに、マスカット・ベリーAの皮が溶けやすく、色素自体も強くないことがある。ピノ・ノワールなどのヨーロッパ系品種と比較すると、より短いマセラシオン期間でピークを迎えることがわかってきた。
「14〜15日目に香りのピークを迎えるようです。このタイミングであれば、香りに複雑味があり、スパイシーさも感じられます。マセラシオンの期間を最適化することで、果実感と共に茎の香りも出るため、ベストなバランスになるでしょう」。
岩﨑さんはテストを繰り返しながら、より満足のいくマスカット・ベリーAのワインを目指す。

▶︎熟成容器にもこだわる
「2024年ヴィンテージでは、マスカット・ベリーAを使って、ロゼワインと赤ワインを造りました。ロゼは気軽に飲める味わいに仕上げて、2025年3〜4月頃に直販でリリースします」。
また、赤ワインは高級レストランなどに卸す予定だ。複雑味が魅力のワインなので、寿司屋のコースメニューの最後にペアリングするイメージだ。穴子やうなぎ、川魚などと合わせることを想定している。
深みあるマスカット・ベリーAを生み出すため、熟成容器にもこだわっている岩﨑さん。2025年ヴィンテージ以降のワインは、新樽と陶器タンクでそれぞれ熟成をおこない、最終的にブレンドしてひとつのワインに仕上げる予定だ。
「陶器タンクは、ヨーロッパの銘醸地でも多く使用されているメジャーなタンクです。コンクリートタンクや、素焼きの陶器であるクヴェヴリやアンフォラのデメリットをカバーしているのが陶器タンクです。フランス留学時代の修士論文のテーマが『容器による熟成の味わいの違い』だったので、これからも熟成容器にはこだわっていきたいですね」。
陶器タンクとステンレスタンクの比較実験を行った経験があるという岩﨑さんは、陶器タンクでフレッシュ&フルーティーな味わいがキープできることを実証済みなのだ。陶器タンクは微量な酸素透過がありつつも、水漏れやコーティングが不要である点に特徴がある。
一方、コンクリートタンクでは、石灰とワインに含まれる酒石酸が反応してしまうため、樹脂などでのコーティングが必要だが、コーティングには手間とコストがかかる。さらに、素焼きのクヴェヴリやアンフォラは低温で焼き上げた陶器であるため、微細な穴が多く酸素を通しすぎるという欠点があり、ワインが酸化しやすくなってしまう。粗悪なものだとワインが漏れてしまうケースもあるという。
「その点、陶器タンクはワインが壁に染み込みにくいので、赤ワインに使った直後に洗って、すぐ白ワインに使うことも可能です。イタリアの大手メーカー製の陶器を導入したので、熟成に使うのが楽しみですね」。
岩﨑さんのこだわりが詰まったマスカット・ベリーAは、今後もさらなるブラッシュアップが続いていくことだろう。

『まとめ』
最後に、ワインづくり以外の取り組みや、今後の展望を紹介していこう。
「私が目指すのは、ワイン造りを通して地域の魅力を発信することです。また今後は、ワインだけでなく、『ラタフィア』というリキュールの製造にも取り組みます」。
ラタフィアとは、ぶどうの果汁にブランデーを添加して発酵を止めたもの。ぶどう由来の自然の甘さが残った、素朴な味わいのリキュールだ。岩﨑さんがラタフィアの製造を決めたのは、地域のぶどう農家で栽培されたぶどうを無駄にしないため。生食用ぶどう農家が多い栃木市大平町では、規格外の果実や直売で売れ残ったぶどうの多くが廃棄されているのが現実だ。地元の農作物を余すこと無く製品にして、地域の恵みにするとともに魅力を発信するためのツールとする。その実験的な取り組みが、今まさにスタートしようとしている。
さらに、地域資源を活用する企画も次々と打ち出している。栃木の大手革製品メーカーとのコラボレーション企画として、ぶどうの搾りかすを革製品の色染めに活用しようという試みだ。
「その他にも、地元企業やブリュワリーなどとのコラボレーションを考えています。『栃木を盛り上げたい』という思いで、国内外に大きく発信していきます。ワイン造りのみにとどまらず、地域のためにできる活動を積極的にしていきたいですね」。
岩﨑さんの言葉の全てから感じられるのは、出身地への思いの強さだ。東京から車で1時間半ほどの好アクセスというメリットを生かし、ワイン造りで地元を盛り上げていく。岩﨑さんの活動は、2025年2月に開催された「栃木市主催ビジネスプランコンテスト」において、栃木市初のワイナリー設立構想で最優秀賞を受賞。審査員からも「夢がある」と評価された取り組みに、これからも注目していきたい。

基本情報
| 岩﨑元気さん 圃場所在地 | 栃木県栃木市大平町 |