『メルシャン』『マンズ』『サッポロ』ら大手ワインメーカーの集まる山梨県甲州市勝沼町。丸藤葡萄酒工業は日本ワインの本拠地、勝沼町で創業130年を迎えた老舗ワイナリーだ。
丸藤葡萄酒工業は日本ワインの成長を牽引してきた最も重要なワイナリーの1つであり、その歩みを辿ることはそのまま日本のワインの歴史そのものを紐解くかのようである。
今回はワイン醸造に携わって50年の、丸藤葡萄酒工業の大村さんに、ワインとともにこれまで歩んできた道のりを語ってもらった。
『丸藤葡萄酒工業の歴史』
丸藤葡萄酒工業のワインとの関わりは、大村さんの高祖父の代にまで遡る。
昭和初期から養蚕業が衰退していき、桑栽培の代わりに勝沼町ではぶどうを中心とする果樹栽培が盛んになった。
しかし生食用のぶどうは市場に出荷し、競りにかけられるため自分たちでは価格が決められず、生産者の生活は安定しなかった。自分たちで価格が決められる二次産業への道、それがワイン造りだった。
「大日本山梨葡萄酒会社(現・メルシャン株式会社)の影響も多分に受けました。生活のためにワイン造りを始めたと言っても過言ではありません」
勝沼町藤井の大地主であった大村忠兵衛氏が大日本山梨葡萄酒会社(現・メルシャン株式会社)設立の際、勝沼の2人の青年にワイン造りの研修を受けさせるためフランスのトロワに送った。
その際、株式会社組織にしなければならず、その出資者の1人として名を連ねたのは明治10年(1877年)のことだった。そして、ここからワイン業界への関わりが始まった。
その後、明治15年(1882年)に忠兵衛氏の息子である大村治作氏が葡萄酒醸造を開始。明治23年(1890年)に治作氏が創業し、正式に葡萄酒醸造免許を取得した。その後二代目の大村澄蔵氏、三代目の大村忠雄氏、そして四代目である大村春夫さんにまで受け継がれ、現在の丸藤葡萄酒工業がある。
丸藤葡萄酒工業という社名にも、その歴史の足跡は残されている。
「丸藤」は地元地域である藤井の名を背負った昔からの屋号と、大村家の家紋が下がり藤であることから付けられた名前。古い工場の入り口の大戸には下がり藤の家紋が入っていたそうだ。
「丸藤葡萄酒工業の工業だけ邪魔だよねって言われるんですけどね。昔、ブランデーの醸造免許も持っていたので、なんでもできるようにってことで親父たちの代で考えたんです。古いワイナリーには『工業』と ついていることが多いんですよ。何度か改名しようと思ったこともあったんです。でもかえって今はこれもレトロでよかったかな、と思っています」

また、大村さんのワインの原風景、と思える話がとても印象的だったので紹介したい。
「昭和30年代終わり頃、おばあちゃんがね、夏の暑い昼下がり、冷蔵庫にワインを冷やしておくんですよ。それで、その頃は豆腐屋さんが自転車の荷台に豆腐を積んで回ってくるんですけどね、だまってても豆腐を一丁置いていくんです。
だけどお金を払っているところは、見たことがなかったんです」
台所の手前のたたきの部分に、テーブルと椅子が設置してあった。そこへ豆腐屋さんは腰をおろすのだ。そして大村さんのおばあさんはビールを飲むようなコップに冷やしたワインを注ぐ。豆腐屋のおじいさんはそれを一杯、ギューっと飲んで、キセルでタバコをふかして帰っていくのだ。
ポートワインの名残りがある時代、生ぶどう酒はまだ一般的に普及していなかったが、豆腐一丁とグラス1杯のぶどう酒との物々交換が成立していたのだ。
「その当時は生ぶどう酒に、少し砂糖を入れて飲むんだよ、って聞いてましたね」と大村さん。大村さんのおばあさんの出す、冷えたワインと豆腐。そのお金を介さないやりとりが古き良き時代を忍ばせる。
大学卒業後には醸造試験所(東京都北区滝野川。現在は旧醸造試験所として重要文化財指定)でワイン醸造を学び、その後フランスのボルドーI.T.V(ぶどう・ぶどう酒研究所)とボルドー大学へ留学をする。
父である先代が病気がちだったためフランスからは1年ほどで帰国した。
「ジュ・テームだけ覚えて帰ってきたんですけどね」と大村さんは笑うが、才気にあふれた青年時代の大村さんが、このフランス留学で吸収したことは決して少なくなかったはずだ。
大村さんのフランスでの経験は留学時の知人とのつながりも含め、その後の丸藤葡萄酒工業の歩みに要所要所で重要な役割を果たしている。

▶第一次ワインブームの訪れ
学生時代、大村さんは東京・高円寺に住み、卒論の作成中と卒業後には滝野川の醸造試験所でワインの勉強を2年経験してから勝沼へと戻る。
その1年後に渡仏し、帰国後から丸藤葡萄酒工業でワイン醸造を始めた。
大村さんが醸造試験所に通っていた昭和49年頃は国民1人当たりのワイン消費量は年間200ml、牛乳瓶1本分しかなかった。醸造試験所まで電車を乗り継いで通う間、行き交う多くの人たちがみんなハーフボトル1本ワインを飲んでくれたら、ワイン消費量が上がるのに、と毎日のように思ったそうだ。
ちょうどその頃、マンズワイン、サントリー、メルシャンら大手ワインメーカーが一斉にテレビコマーシャルを打ち始めた。これから日本でもワインの時代が来るとのことで、大手ワインメーカーがこぞってワインの普及に力を入れ出し、第1次ワインブームが起こった。
ホテルでワインパーティが開かれるようになったのもこの頃だ。
しかし、当時はまだ甘口のワイン全盛期で、9割のワイナリーが甘口ワインを造っていた。辛口ワインを造っていた残りの1割のワイナリーも、実は醸造量の1割程度を辛口で造るのみでほとんどは甘口を造っている、そんな状況だった。
「仁義なき戦いの親分役をしていた俳優、金子信雄さんがやっていたレストラン『牡丹亭』が荻窪にあったんですよ。そこのシェフ、小沢幸一さんは厳しい人で、『今回送ってきたワインは俺の料理に合わねえー!』って電話をかけてきたんです。
だったら、よそのワインを使えば良いのに、なんでわざわざ電話をくれたんだろうと思いましたが、若かったから腕まくりして、シェフの鼻を明かさんといかん!ということで、売れても売れなくても、料理に合う辛口ワインを造ることにしたんです」
大村さんと同時期にフランスに留学していたマンズワインの知人とは「日本は甘口のワインが多いけど、これからは辛口ワインを造らなきゃダメだよね」と、お互いに励まし合える関係だったことも、大村さんの背中を押す要因だったようだ。

▶垣根栽培へのチャレンジ
世間の流れに負けることなく料理に合う辛口ワインを造り続ける、と大村さんが決意した時期は、海外からのワインの関税を引き下げる動きのあった頃でもあった。日本が車や、家電品、コンピュータなどを輸出すれば見返りに何か買わなければならない。日本のワイン産業は脆弱だったので輸入ワインの関税を高くして守られていたが抗しきれず、関税を下げることになった。
欧州のワイン産地から日本市場に安くて美味しいワインが大量に入ってくる。このままでは日本のワイナリーは立ち行かなくなると思ったそうだ。
そこで、丸藤葡萄酒工業創業からあと2年で100周年という時に、大村さんはもう一つ大きな決断を下した。垣根栽培への挑戦である。
「ともかく100年は続けよう、100年経ったら会社を閉めてもいい」
ただ、辞めるのはいつでもできるので、悔いを残さないようにしようと思った。欧州系品種と米国系品種の交配品種は父の時代から何種類か棚仕立てで栽培していたが、ことごとくうまくいかなかった。
日本は収穫時期に秋雨が多く、垣根栽培は無理だと言われていた。しかし、これを確かめた人がいるのだろうか?
甲州ぶどうには伝統的に棚で栽培してきた1000年もの歴史がある。おのずと醸造用ぶどうも棚栽培が当たり前になっていた。それで大村さんが留学先のボルドーからカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マルベックなどの品種を送り、同じ頃ドイツのガイゼンハイム研究所に留学していた大村さんの友人がドイツ系の品種、リースリングなどを日本に送ってくれた。
海外から日本に輸入された苗木は、病害などの問題がないかチェックするため、国の隔離圃場に1年間預けられた後、大村さんたちの手元に届いた。これが1970年代末の事である。しかし、届いた苗木を棚で栽培したがワイン用ぶどう栽培技術が未熟だったためことごとくうまくいかなかった。
1980年代末に輸入ワインに席巻されると感じていた大村さんは、同じ勝沼で垣根栽培に着手していたマンズワインのレインカット栽培に飛びついた。
レインカット(垣根専用の雨除け栽培システム)の生みの親、栽培担当の志村富男さんの指導を受け、丸藤葡萄酒工業でも藁にも縋る思いでレインカット栽培を採用。
大村さんの長女の名を冠した自宅横の「彩果(あやか)農場」にカベルネ・ソーヴィニヨンを植え、垣根栽培を1989年にスタートさせた。
「植樹して2〜3年は比較的良い結果が得られたので、栽培はチョロイもんだと思うようになりました。シャルドネや他にもいろいろな品種も植えたけど、実は苦労の始まりでその後は思ったほどでもなく、今に至るまで苦労の連続!」と大村さん。
数年後、垣根用の新しい畑を開設した折、志村さんから勝沼にはプティ・ヴェルドが良いのではないか?とすすめられ、台木だけ挿しておけと大村さんは言われた。穂木は用意するからということだったが初年度3芽、2年目も3芽しか出なかった。
「メルシャンにも同じプティ・ヴェルドの穂木があるので貰え!」という志村さんの意見を受け、大村さんは以前から懇意にしていたメルシャンの齋藤さんから2本のプティ・ヴェルドの枝をもらった。
しかし、ここでアクシデントが発生。齊藤さんから電話がかかってきた。
「大村さんごめん!間違えた!グロセミヨンをあげたみたいだ、引っこ抜いてくれ!」代わりに2本の新しい枝をもらった。実がなるまでは解らないので観察すると、確かに最初にもらった枝からは白ぶどうが実った。そして新しくもらった枝にはプティ・ヴェルドが実り、大村さんはこの枝を順次増やしていった。カリフォルニアのデイビス校の留学を終え、帰国したばかりの齋藤さんが品種を間違えても不思議ではなかった。
このように、丸藤葡萄酒工業の垣根栽培はマンズワインの指導のもとに始まり、幾多の苦労を重ね、現在は赤品種でカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルドなどを垣根栽培で作っている。
そのほか、白品種ではシャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなどを従来の棚栽培でも作っている。
赤品種は前述の3品種のほかに、温暖化の影響をふまえてタナとアルモ・ノアールも育てており、そこにシラーも加わる。

また、丸藤葡萄酒工業では農家との契約栽培も行っている。1998年に赤ワインの大ブームが起こった頃、赤ワイン用のぶどうが足りなくなって、長野県塩尻市の桔梗ヶ原の知人に頼んで13人ほどの農家に組合を作ってもらい、メルローの栽培を依頼した。
「契約農家さんとの付き合いはもう、22年が経ちますね。今では契約農家さんもだんだん減って5人くらいになりました」と大村さん。毎年20トンほど収穫できていたぶどうも、今では15トンほどになっているという。
大村さんは長年垣根栽培を続けたうえで、再び考えを新たにしつつある。
「レインカットに慣れてきて、あれは違う、これは違う、とか色々なことを自分たちで改良するようになり、むしろ棚栽培で、密植仕立てでやった方がいいんじゃないか、と最近思うようになりました」
ぶどう栽培に約50年関わってきた大村さんだからこそのこの見解は、日本のワイン用ぶどう栽培にとって非常に貴重な意見なのではないだろうか。

▶大手メーカーとのつながり
丸藤葡萄酒工業のぶどう栽培・ワイン醸造はマンズワインやメルシャンなど、近隣の大手メーカーのつながりに支えられてきた部分が大きいという。
「1970年代後半、メルシャンの工場長、浅井昭吾(ペンネーム:麻井宇介)さんが、『メルシャン1社だけ良くてもダメだ!みんなが良くならなければ産地、勝沼は認められない!』と言って、醸造技術の情報公開をして下さいました。
メルシャンでは学識経験者やソムリエなどを呼んで年1回『新酒を唎く会』という会を開いていました。この会は山梨税務署管内の人たちにも参加を呼びかけ、我々も参加することができました。その影響はとても大きかったと思います」
甲州やシャルドネなどに用いられる白ワイン特有の、すぐには澱引きを行わない醸造方法である『シュール・リー』の技術も、『新酒を唎く会』で識ることができたという。
「シュール・リーということは一番初めにメルシャンさんが言い始めて、僕たちは『どういうこっちゃ。』という感じだったんです。『新酒を唎く会』では樽の中が見えるように、鏡の部分をアクリル板にし、反対から光を当てると中の澱の状態がつぶさに見られました」
1984年にメルシャンが1983年のぶどうで甲州シュール・リーを発表した。それを初めて飲んだ時、大村さんは「甲州でこんな美味しいワインができるのか!」と驚いたという。その後1988年から丸藤葡萄酒工業でも甲州シュール・リーを造り始め、今では主力商品になっている。
また、丸藤葡萄酒工業とメルシャン、マンズワインら5社で『シュール・リークラブ』を結成。勉強会を開き、情報交換を行った。
「大手さんが情報公開してくれたおかげで中堅どころのメーカーも今のようなワインを造れている。自分一人で大きくなったような顔をしたらいけないな、といつも思っています。マンズワインには栽培、メルシャンには醸造、サッポロワインには設備のことなどを学びました。恩返しは、いいワインを造ることだと思っています」
大村さんは力強くそう語った。

『自社圃場の土壌・農法について』
「土壌に関しては理想的な場所を選んで植えるということよりも、今所有している畑にぶどうを植えていくしかない、という部分が大きいです。畑によって、のっぺだったり、まつちだったり、色々です」と大村さん。
山梨の言葉で火山灰土を『のっぺ(のっぷい)』といい、粘土質土壌を『まつち(真土)』というのだそう。
圃場は土をあまり耕さない不耕起栽培を行い、雑草を生やしたままの草生栽培を行っている。肥料もあまり使用することがなく、ときどき微量要素を葉面散布する程度で、あとは刈った草をそのままにしておいて自然に栄養分にしている。
「除草剤もほとんど使っていません。除草剤が全て悪いとは思っていませんが、化学肥料みたいなものもそんなに撒いてないですね」
丸藤葡萄酒工業のぶどうは減肥料・減農薬の自然に近い環境で育てられているのだ。

『丸藤葡萄酒工業のこれから』
丸藤葡萄酒工業では地球温暖化の問題にも積極的に取り組む方針だ。
「2015年にフランスがCOP21(第21回気候変動枠組条約国会議)で提案した取り組み『4パーミルイニシアティブ』では、切った枝をただ燃やすのではなく、炭にして土に戻すことで、排出しているだけの炭酸ガスを貯留すると言われています。このような対策はこれから日本でも提唱されると思います」
また、地球温暖化はSDGs(持続可能な開発目標)にも関係する問題だと大村さんは言葉を継ぐ。
ただ生産性を上げるためだけにやみくもに熱を出してもいいわけではない。これからの子供たちの世代に向けてこの環境を守るため、みんなで環境問題を考えることが大切である。
次の世代の行く末を見つめる大村さんの眼差しは優しく、そして強い。

▶適地適作とテロワール
「昔の人は、適地適作ということを言ったが、ことワイン用ぶどうに関しては昔の人はそんなことやっていなかっただろうと思っていたんです。でも、だんだんやればやるほど、適地適作という言葉が身に染みて分かるようになってきましたね」
フランスにはテロワール、という言葉があり、ワインの世界では頻繁に用いられる。
「テロワールは、土壌、もっと広く言うと風土という意味があります。メルシャンの浅井さんは『テロワールの中には人間の営みも入るんだ。美味しいワインを造るという高い志を持った人間の営みが、テロワールの1つを構成しているんだ。』と言っていて、僕はなるほどな、と思いました」
適地適作とテロワール。その2つのキーワードから導き出される丸藤葡萄酒工業のこれからのぶどう栽培はどのようなものになるのか。
「白ワイン用品種だとシャルドネとソーヴィニョンブランを作っているけれど、ソーヴィニョンブランはタンパク質が多いので、にごったりしてなかなか厄介ですね。面白いけれど。甲州は長年やっているので、大事にしていきたいです」
赤ワイン用品種に関してはどうか。
「うちの中ではプティ・ヴェルドが一番いいですね。2012、2013、2014年度の日本ワインコンクールでは金賞を受賞し、特に2012年のものは出来が良く、伊勢志摩サミットにも使われました。タナも作ってますが、色が濃く、タンニンが強い品種でこれも面白いと思います」

あくまでも、土地に合ったものを作り続けるという方向性だ。
「無理をして合わないものをやっても、長続きしないんですよ。兎にも角にも、良いぶどうができれば、あとは基本に忠実にしていれば良いワインは造れます」そう大村さんは断言する。ぶどう栽培・ワイン醸造に関わって半世紀になる大村さんだからこその、重みのある言葉なのではないだろうか。
「まだまだわからないことはたくさんあります」と大村さん。キャノピーはどうしたらいいのか、畝間や株間は何センチが良いのだろうか…。トライアンドエラーを繰り返すしかないという。大村さんたちは長年の経験を経て、これからも真摯に地道な努力の道を歩んでいくのだろう。

▶丸藤葡萄酒工業が目指すワインと未来
丸藤葡萄酒工業では日本食などの家庭料理に合うようなワインや、ビストロのような空間で、隣同士和気あいあいと気軽に食べられる料理と合わせて飲んでもらえるような、そんなワイン造りを心がけてきた。
大村さんにはこんな思いがある。
「フレンチに合わせるだけでなく、一家団らんの場でみんなが食事に合わせて飲める、そんなワインにしたい。値段もあまり高くしたくない」
また、大村さんは「これからはなかなか他で飲めないような、熟成して味の出るようなワインが必要とされると思うんです。やっぱり、何年か熟成させないと美味しくないよね、というようなことになっていくと良いな」と熟成タイプのワインにも力を入れていきたいと語る。
さらに消費者教育にも意欲を見せている。
「ワインを料理と楽しむという考え方がまだまだ浸透していない。これからは家庭料理にはこれ!って提案することが必要。今はまだ難しい状況だけど、レストランに集まってワインと一緒に料理を楽しんでみよう、というような取り組みもしてみたい」と大村さん。
ワインをただ造って売るだけではなく、ワインの奥深さを知ってもらいたい。ワインの歴史や料理との相性など、楽しさを知り、ワインの世界に入ってもらいたい、と考えている。
「ぶどう栽培の手伝いや収穫に来てもらう、という取り組みもしたいんですが、事前にスケジュールが決められることではないので、なかなか難しいんです。でもやりたいという思いはあります。
会員制度はあまり好きではないんですが、以前5年間で60本ワインを届ける『Rクラブ』という会もやっていました。現在、営業のいない丸藤葡萄酒工業の応援団を買って出てくれているのはこの時の会員さんだったりするんですよ」
また、コロナ禍で実際のワイナリー見学が難しい状況であるが、バーチャルでのツアーも視野に入れ始めたのだとか。
「本来の見学では見せられない部分もバーチャルでなら見せられるかもしれません。この状況を逆に生かしていきたいですね」
大村さんはコロナ禍の中にあってもあくまで前向きな姿勢を崩していない。
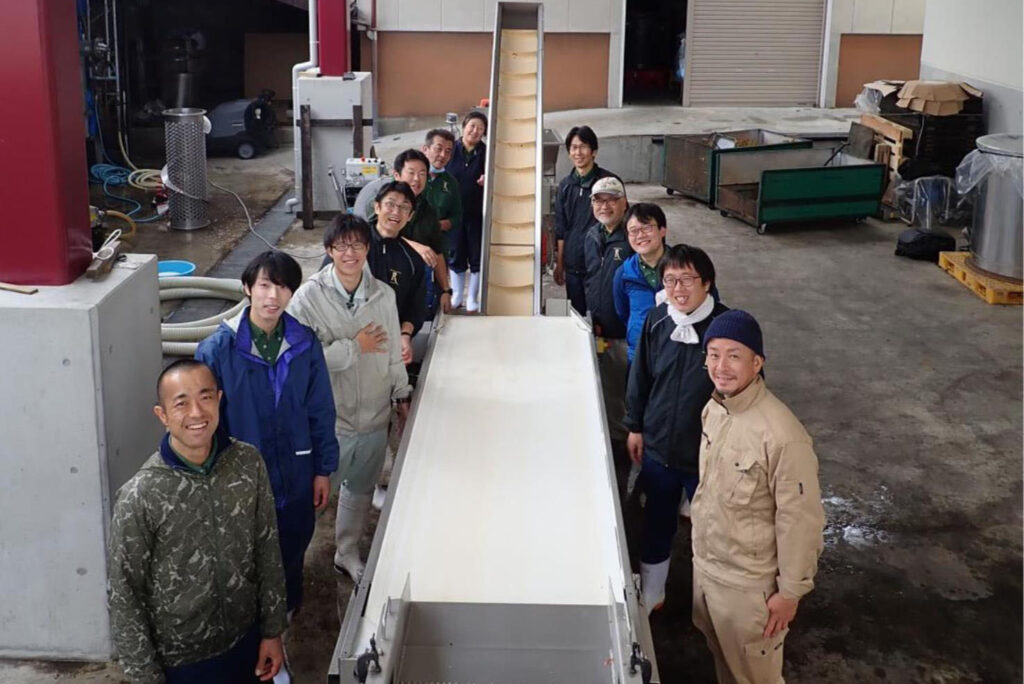
『まとめ』
「日本のワインはまだまだやることがいっぱいある。世界の銘醸ワインと肩を並べられるようなワインを造りたいですよね!」と、日本ワイン界屈指のベテランながらいまだ意欲旺盛な大村さん。そんな大村さんがその昔、父である先代とよく話していたことがあるという。
「ワイン1本で心触れ合えるような温かい交流がほしいね。ワインのボトルとお金だけの交換はやめような、ってよく話していました」
かつて子供の頃に大村さんが見た、ワインと人との原風景が、彼の長いワイン人生とその情熱の基盤になっているのかもしれない。
長い伝統と人との触れ合いを大切に守りつつ、技術刷新への情熱を絶やさない丸藤葡萄酒工業は、間違いなく日本ワインを代表するワイナリーの1つであり、人とワインの織りなす日本ならではの文化を牽引する存在に、違いないだろう。

基本情報
| 名称 | 丸藤葡萄酒工業 |
| 所在地 | 〒409-1314 山梨県甲州市勝沼町藤井780 |
| アクセス | 車 中央自動車道 勝沼インターチェンジを甲府方面におり、国道20号線の四つ目の信号(交差点名『藤井』)を左折、上り坂を200mほど上った左手が当社です。 電車 新宿-特急スーパーあずさ-大月-中央本線-勝沼ぶどう郷 新宿-中央線中央特快-八王子-中央本線-勝沼ぶどう郷 新宿-京王線特急-高尾-中央本線-勝沼ぶどう郷 |
| HP | https://www.rubaiyat.jp/ |








