「いにしぇの里葡萄酒」は日本有数のワイン産地、長野県塩尻市の北小野地区に、2017年に設立されたワイナリーだ。
塩尻市のなかでも、桔梗が原や岩垂原・柿沢などの地区は全国に広く名を知られているが、北小野はいにしぇの里葡萄酒がパイオニアとなって開拓した新しいワイン産地。
今回は塩尻の最新ワイン地区である北小野のワイナリー、いにしぇの里葡萄酒の代表である稲垣雅洋さんにお話を伺った。
『いにしぇの里葡萄酒創業の背景』
東京で料理人をしていた稲垣さん。東京生活に終止符を打ち、2005年に故郷の塩尻市に戻ってきた。地元で自分の料理店を開くことも視野に入れていたが、明確な計画を立ててはいなかったという。
そんなとき、塩尻市でぶどう収穫の季節アルバイト募集に出会った。このアルバイトこそが、稲垣さんをワイナリー創設へと導くきっかけとなったのだ。
▶ぶどう収穫のアルバイトで運命的な出会い
「もともと洋食のレストランで働いていたこともあり、ワインは身近な存在でした。ですが、当時は自分がワイナリーを設立するなど、考えてもみなかったですね」。
稲垣さんのアルバイト先は、地元塩尻市の老舗ワイナリーである「信濃ワイン」。ぶどうの収穫だけではなく、ワイン醸造の手伝いも経験した。ぶどう栽培やワイン醸造のさまざまな工程について知るたび、ワイン造りに興味を持つようになった。さらに、稲垣さんにとって重要な出会いも経験したのだ。
稲垣さんが信濃ワインでアルバイトをしていたのは2005年のこと。さかのぼること1年、実は塩尻ではあるワイナリーが創業した。「城戸ワイナリー」だ。そして、城戸ワイナリーの立ち上げに関わったメンバーが、たまたま稲垣さんと同じ時期に信濃ワインに在籍していたのだ。
塩尻で新しくワイナリーを立ち上げた人がいるとの噂を耳にしていた稲垣さん。城戸ワイナリーのオーナー、城戸さん夫婦を紹介してもらい、会うことになった。
▶小規模ワイナリーの挑戦に胸を打たれる
城戸ワイナリーは、夫婦だけでぶどう栽培からワイン醸造までを手がける小規模ワイナリーだ。今でこそ塩尻には個人経営のワイナリーが増えたものの、2005年頃には珍しい存在だった。塩尻で新規ワイナリーが創業したのも何十年ぶりかのことだったのだ。
塩尻といえば、当時は信濃ワインや井筒ワインなど規模が大きなワイナリーが主流だった。そんななか、個人でワイナリーを立ちあげたことに稲垣さんは興味を抱いたのだ。
城戸夫妻に会って話を聞くうちに、「世界基準のワインを造りたい」という城戸さんらのあふれる情熱と意欲に魅了された稲垣さん。
「その場ですぐに、お手伝いさせてくださいと頼みこみました。あとからわかったんですが、そのとき城戸さんには『怪しい奴が来た』と思われていたらしいんですけどね」と、稲垣さんは苦笑いする。
信濃ワインでのアルバイトと並行して、城戸ワイナリーでの手伝いもはじめた稲垣さん。城戸ワイナリーでの経験をとおして、栽培から醸造・販売までの一連の流れを学んだ。
また、「ワイン造りにおいて、いかに原料のぶどうが大切であるかということも、このときに身をもって知りました」と稲垣さんは話す。
城戸ワイナリーでの経験を経て自分でもぶどうを栽培してみたいと考え、まずは実家の畑にぶどうを300本植えた。自らのワイナリーである、いにしぇの里葡萄酒の設立に続く道のりを歩み始めたのだ。
『ピノ・ノワールから始めたぶどう栽培』
稲垣さんが最初に植えたぶどうの樹はピノ・ノワールだった。城戸ワイナリーへの手伝いに通っていた当時、後に愛知県豊田市のワイナリー「アズッカ・エ・アズッコ」を経営することになる須崎さんも研修に訪れていた。稲垣さんは、須崎さんと城戸さんと共に、ワイン会をするなどの交流を持ち、刺激を受けた。
「須崎さんが愛知に帰ってぶどうを植え始めると知りました。そこで、自分もなにか植えたいと相談をしたんです」。
塩尻で多く栽培されているワイン用ぶどう品種のひとつにメルローがある。しかし、メルローは寒さに弱い。稲垣さんの畑がある「北小野地区」は標高約850mで、塩尻の中心地区よりも100m程度高い場所にあるため冷害が懸念された。北小野はもともと果樹の栽培自体が難しいとされる地域で、周辺にぶどうを栽培している農家も皆無だったのだ。
須崎さんや城戸さんらからも、メルローは難しいのではとのアドバイスを受けた稲垣さん。ドイツや北海道など、厳しい寒さに見舞われる土地でも栽培されているピノ・ノワールなら栽培できるのではと考えた。
しかし、ピノ・ノワールは栽培が特に難しい品種として知られている。「今の自分なら最初に挑戦する品種には選ばないですね。当時、ぶどう栽培について知識がなかったからこそできたことかもしれません」。
しかし、稲垣さんの挑戦は功を奏した。栽培を進めるなかでさまざまな難しさに直面したものの、現在では満足のいく品質のぶどうが収穫できるようになった。

▶8種類のぶどう品種を栽培
ワイナリーの設立を具体的に検討しはじめた稲垣さんは2014年、塩尻市が開講している「塩尻ワイン大学」の1期生としてぶどう栽培やワイン醸造などについて学んだ。ちょうどその頃には、メルローはたしかに寒さには弱いが赤ワインの主力品種として採用が可能なことがわかってきた。
いにしぇの里葡萄酒では、ピノ・ノワールを含め8種類のぶどう品種を栽培している。 現在の主力品種は赤がメルロー、白がシャルドネだ。
白ワイン用に選んだシャルドネは、周辺地域での栽培実績をもとに選択した。最初に手がけたピノ・ノワールのほかにもリースリングなどのドイツ系品種を少しずつ増やしている。

▶越冬が成功の鍵をにぎる
山梨のように温暖な土地では近年、夜温の下がりにくさが問題視されている。昼夜の寒暖差がなくなるとぶどうの糖度は上がるが、酸が減りやすくなるためだ。ワイン用ぶどうは酸が重視されるため、酸が残りつつ熟せる環境が望ましい。いにしぇの里葡萄酒のある北小野は標高が高いため、寒暖差が激しいのが特徴だ。
「寒暖差のある北小野は、酸が残るぶどうを作るうえで、適した環境だと思います。ただ、問題は冬ですね」。
標高が高いいにしぇの里葡萄酒の畑では冬季に凍害にあいやすく、越冬対策が毎年大きな課題となる。寒さ対策として、植えてから3年目くらいまでは樹に藁を巻いた。苗木のうちは特に凍害にあいやすいため丁寧にケアをする。
北小野では春から夏の日照量はじゅうぶんに確保できる。ただし、春先の遅霜には注意が必要だ。5月頭くらいまで霜が下りる危険がある。ぶどう栽培を始めてすぐの頃には、芽吹きの時期に霜にやられるという苦い経験もした。
最近は遅霜が少ないので被害はないが、天候の予測は難しいので、年によってはどうなるかわからない。そのため、遅霜の影響を考慮すると芽吹きの早い「早熟系」の品種は選定の候補にあげにくい。
「サステナブルな観点からすると土地にあった品種をみつけるべきで、手のかかる品種は作れません。これからも適種を模索しながら栽培を続けます」。

▶肥沃な黒ぼく土
北小野地区にあるいにしぇの里葡萄酒の畑は、塩尻の土壌に典型的な火山灰の黒ぼく土。肥沃な土質で、昔からレタスなどの高原野菜が作られてきた歴史をもつ。
表層50cmほどの黒ぼく土の下は赤土だが、水と栄養が豊富な土地ではぶどうの根は土の表層を張っていくのみ。黒ぼく土以外の影響は受けることはなさそうだという。肥沃な土壌であるため施肥はほぼ必要ない。ただし、土壌分析しながら石灰や塩尻全域で足りない傾向があるマグネシウムなどを足すこともある。
果樹栽培には難しいといわれてきた北小野だが、高品質なぶどう栽培が可能なポテンシャルを秘めている土壌だといえそうだ。
▶土地にあった栽培方法
いにしぇの里葡萄酒の栽培方法は、垣根仕立てが基本だ。ナイアガラのみ「ジェノバダブルカーテン仕立て」を採用している。カーテン棚栽培の要領で枝を一度上にあげ、新梢をカーテンのように垂れ下げる栽培方法だ。
「ナイアガラのように樹勢の強い品種は、垣根にすると枝が暴れて実を付けないことがあるのです。そのため、枝を下に向けることで樹勢を抑える試みをしています」。
ワイン専用品種のぶどう栽培は、垣根仕立てと棚仕立てが主流。ジェノバダブルカーテン仕立てとは耳慣れない手法かもしれない。高温多湿な日本の気候に向いた仕立て方法で、近年は山梨県などで導入するワイナリーが増えているそうだ。
「ほかにも『スマート仕立て』といって棚を使って垣根のように仕立てる方法など、土地にあった仕立て方がいろいろとあるのですよ」と、稲垣さん。自らの土地に合う栽培方法のために研究を重ねてきたことが推察できる。

▶必要な作業はできるだけ前倒しで
2021年前半は天候が芳しくなかった。梅雨明けは早かったが、梅雨明け後からの雨が多かったのだ。7月中旬から1ヶ月ほど天候が悪く、ぶどうの熟度があまり上がらなかった。しかし幸いにも、8月の終わりからは天候が回復。平均すると標準的な天候の年だったというのが稲垣さんの印象だ。
「秋雨や台風などの影響がなかったことは非常に助かりました。収量も確保でき、病気もあまり出ませんでした」。
いにしぇの里葡萄酒では、前シーズンである2020年に長雨の影響で「べと病」の被害が出た。葉に発生したべと病がぶどうの実にまで蔓延して、「実べと」になったのだ。
そのため、2021年は7月上旬には早々にレインプロテクションをおこなった。ビニールを房の上部にかけて雨除けにする方法だ。例年は秋雨や台風の対策としてお盆過ぎくらいからレインプロテクションを実施していたが、時期を早めることで「実べと」の発生を免れた。
病気対策には、防除のタイミングも重要だ。雨が続く天候だったとしても、降雨の前にタイミングよく防除ができると病気を減らすことができる。
「天候が悪くてもうまく作る人は作るんですよ。特に、経験豊富な年配の方はタイミングを図るのがうまいですね。同じ条件でもできる人がいるのだから、自然のせいにはできないですね」。
稲垣さんは、必要な作業をできるだけ前倒しでおこなうように心がけているそうだ。自然相手の農業とワイン醸造を成功させるための極意のひとつだといえそうだ。
▶糖度よりも熟度を重視
いにしぇの里葡萄酒がぶどうの収穫時期の判断をするうえで大切にしているのは、「種の熟度」だ。ぶどう栽培において、収穫タイミングの見極めには糖度を基準とすることが多い印象だが、稲垣さんはぶどうの種の熟度を確認することで収穫の時期を判断している。
ぶどうの種が緑色から茶色に熟してくると、収れん味のあるきついタンニンがまろやかに変化する。種が熟したぶどうを使って醸造されたワインは、品種本来の果実味を発揮するのだという。
「糖度も重要ですが、種の熟度を確認し品種それぞれの味わいが出てくるまで、なるべく待ってから収穫するようにしています」。
種の成熟を待って収穫する場合、収穫時期を通常よりも遅らせる必要も出てくる。いにしぇの里葡萄酒の畑は標高が高いため、低地に比べるとなおさらだ。収穫時期を遅らせると病気のリスクも高くなる。しかし、リスクを冒しても熟度を上げて収穫するだけのメリットがあるということだ。
「ぶどうを皮ごと口に入れて、種もガリガリと噛んでみます。果皮から出てくる風味や種の感じ、タンニンの具合などを確かめるんです。じゅうぶんに成熟していることを見極めてから収穫します」。
ぶどうは分析にもかけるが、自らの味覚や嗅覚など官能的な判断をより重視する。料理人でもある稲垣さんだからこそできる判断方法なのだろう。
『世界基準のワインを目指す、いにしぇの里葡萄酒』
いにしぇの里葡萄酒が目指すのは、世界基準のワインだ。
「世界基準といっても、生産量を増やして海外に売り出すことを指すのではありません。同じ価格の海外ワインといにしぇの里葡萄酒のワインがあった場合、飲み比べてうちのワインを選んでもらえるようなものを造りたいのです」。

▶品質と価格のバランスが取れた、北小野らしいワイン
海外の製品があふれるワイン市場で、日本ワインがもっと評価されるためには、価格と品質のバランスをとっていく必要があると考える稲垣さん。品質と価格のバランスがよいワインを造ることで、自信を持って世界のワインと競えるとの見通しだ。また、北小野のテロワールを表現したワイン造りも目指したいという。
「まだ造って4回目なので、はっきりとはイメージがつかめていないのですが」と、稲垣さんは謙遜する。きっと近いうちに、よりはっきりとした「北小野のワイン」らしさを打ち出してくれることだろう。
▶樽熟成のワインが原点
最近では世界的に、樽を使わず、ぶどうの果実味を重視したワインが主流になってきている傾向がある。樽の香りが付き過ぎたワインはあまり好まれないのだ。確かに、フルーティなワインにもよさがある。だが、樽で熟成したワインには、フルーティなワインにはない複雑な香りと味わいという魅力がある。
稲垣さんがワイン造りの道に進んだきっかけのひとつに、城戸ワインで醸造された樽熟成のメルローとの衝撃的な出会いがあった。しっかりとしたぶどうの果実味に樽の香りが混ざり、深みが生み出されていた城戸ワインのメルロー。「日本でもこんなワインが造れるのか」と、稲垣さんを大いに驚かせた。甘くてちょっと薄めという、当時の日本ワインの典型的なイメージが完全に覆されたのだ。
ぶどうの果実のポテンシャルが低く果実味が十分ではないと、樽の香りに果実味が負けてしまう「樽負け」を起こす。しかし、樽の香りに負けない品質のぶどうを使って樽熟成させると、瓶熟成を経てさらに複雑な香りのワインに仕上がる。
「発酵が終わってすぐの状態と、1年程度樽で寝かせたあとでは、味がどんどん変化していきます。飲み比べると熟成度合いの変化がよくわかるのです。これが樽熟成ワインの素晴らしさであり魅力なのだと感じられます」。
稲垣さんは、樽熟成ワインのもつ魅力を大切にしている。樽をうまく使い、ぶどうの力強さと樽の風味とが一体となったワインを目指しているのだ。

▶幅のある価格帯のワインを提供
いにしぇの里葡萄酒では、商品ラインナップの価格帯に幅を持たせることを重視している。最もリーズナブルなワインは1,000円台で、高価格帯のワインは8,000円程度。商品の価格を決める際には夫婦でテイスティングをおこなう。
「1,000円代のワインを飲んでくれたお客様が、『美味しかったので、次は3,000円のワインを飲んでみようか』と期待感を持って考えていただけるように造っているんです。上の価格帯のワインにもどんどん興味を持っていただけると嬉しいですね」。
新興ワイナリーでは、ナイアガラやコンコードなど低価格帯で販売できるワインを造らない場合も多い。しかし、いにしぇの里葡萄酒では、入門ワインとして購入しやすいワインも造り幅広い層にワインの魅力を発信しているのだ。
▶おすすめは「Niagara 『冬』ほのか」
いにしぇの里葡萄酒の入門ワインとして、稲垣さんおすすめのワインを伺った。教えていただいた1本は、ナイアガラの「Niagara『冬』ほのか」。毎年12月頃にナイアガラの新酒としてリリースされる甘口白ワインだ。飲みやすく万人受けする風味のワインで、気軽に試すことができる1,500円という価格も魅力だ。
「ニンニクを使った料理と相性がよいワインです。アヒージョや塩尻名物の鳥もも肉の揚げ物『山賊焼』とのマリアージュがおすすめですよ。唐揚げや油淋鶏との相性も抜群ですね」。
実は、2021年5月まではワイナリー経営と並行して塩尻駅前で飲食店も営んでいた稲垣さん。料理人ならではのおすすめメニューはすぐにでも試してみたくなる魅力がある。ぜひ、おすすめのワインと料理を味わってみてほしい。

『まとめ』
いにしぇの里葡萄酒では今後も、北小野の土地にあったぶどう品種を見極めて栽培することに重点をおく。生産量を増やすよりもクオリティの向上を優先させていくことを目指すという。高品質で世界基準のワインを造るという目標に向かってつきすすむのだ。
2022年からはしばらく、ぶどう栽培とワイン造りに専念するつもりだという。だが将来的には、北小野に宿泊できるオーベルジュを作りたいとの構想もある。
「まずは、北小野の土地をしっかりと表現できるぶどうの栽培をしていきます。少し先のことになるかもしれませんが、自分の造ったワインと料理を提供して、のんびりと宿泊もしていただけたら最高ですね。もしかすると、10年後には自動運転技術が普及してワインを飲んでも泊まる必要はなくなっているかもしれませんが」と、いたずらっぽく笑う稲垣さん。
どんな未来が待っていても、いにしぇの里葡萄酒のワインの魅力はきっと変わらないはずだ。塩尻のなかでも新たなぶどう産地である北小野から、これからもより魅力を増したワインが発信されていくことを心待ちにしたい。
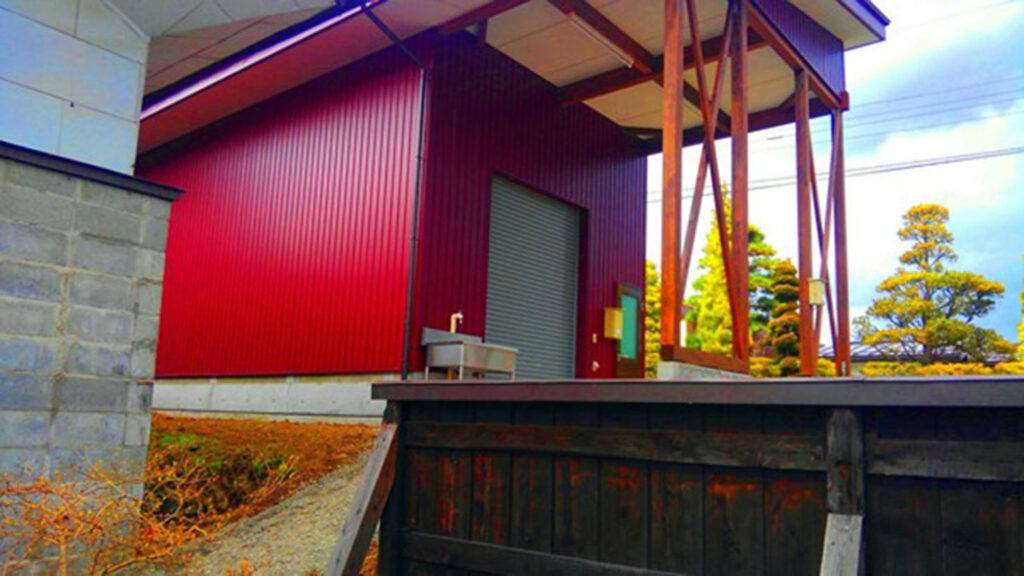
基本情報
| 名称 | いにしぇの里葡萄酒 |
| 所在地 | 〒399-0651 長野県塩尻市北小野2954 |
| アクセス | 【電車】 小野駅から徒歩12分 【車】 塩尻ICから車で11分 |
| HP | https://inishe-no-sato.com/ |








