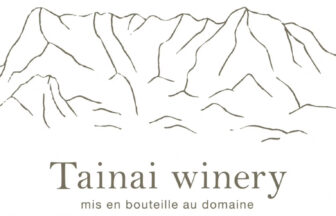ワインとは切っても切り離せない「テロワール」という概念がある。テロワールとは、ぶどう産地の土壌や気候などワインに影響を与える環境要因のことだ。
この「テロワール」を真剣に考え、ワインに表現することに情熱を注ぐワイナリーがある。「グランポレール勝沼ワイナリー」だ。グランポレールは4つの産地のぶどうから、産地ごとの豊かな個性があふれるワインを醸している。
そんなグランポレール勝沼ワイナリーの歴史やぶどう栽培、ワイン醸造のこだわりについて、工場長の久野靖子さんにさまざまな角度からお話を伺った。
ワイン造りへの熱い想いが随所に感じられる久野さんの言葉をとおして、グランポレール勝沼ワイナリーのワインに対する姿勢を読み取ってほしい。
『ワイン事業スタートの経緯』
最初に見ていくのは、グランポレール勝沼ワイナリーが誕生するまでのストーリー。そして、工場長・久野さんの経歴もあわせて紹介していこう。
グランポレール勝沼ワイナリーはどんな歴史を持ったワイナリーなのか、そしてどんな醸造家がワインを造っているのか。ワイナリーを知るための第一の要素である、「人と歴史」に迫ろう。
▶︎ワイン事業の起こり
グランポレール勝沼ワイナリーは「サッポロビール株式会社」が運営するワイン部門だ。サッポロビールの創設は1876年のこと。北海道開拓を目的とした国の組織「開拓使」の施策によって、北海道の地でビール造りが始められた。
そんな歴史あるサッポロビールの「100周年記念事業」として立ち上がったのが、ワイン事業だった。サッポロビールが100周年を迎えた1976年に、グランポレール勝沼ワイナリーの歴史が始まったのだ。
ここで、サッポロビールが100周年記念事業として「ワイン造り」を選んだわけを紹介しよう。
国内で長年「人気のお酒」として王座を占めていた酒はビールと日本酒だった。しかし1970年代にはワインブームが巻き起こり、サッポロビールは市場の流れの変化を敏感に感じ取る。
今後の日本ではこれまで以上に多様なお酒が登場し、市場に受け入れられていくことだろう。ビールのみで勝負するのではなく、新しいことにもチャレンジするべきだという声が、サッポロビールの社内で大きくなったのだ。そして、新しい事業として選ばれたのが「ワイン」だった。
ワイン事業創業の地として選ばれたのは、山梨県勝沼町の綿塚地区だった。勝沼町綿塚では、サッポロビールのワイン事業参入以前から、ワイン造りがおこなわれていた。綿塚がワイン事業創業の地として選ばれたのにも、ワイン造りの歴史がある場所だったからという理由があったのだろう。

▶︎異色の経歴を持つ工場長・久野さん
今回インタビューに応じてくださったのは、グランポレール勝沼ワイナリーの工場長を務める久野靖子さん。今でこそワイナリーで働く久野さんだが、社会人生活は別業界からスタートさせた経歴を持つ。
「最初に就職したのは、携帯電話のキャリア会社でした。しかしワインに興味があったため、会社を辞めてフランスに留学したのです。帰国してからはインポーターで働き、その後、『サッポロワイン』に営業職として入社しました」。
サッポロワインに入社して2年ほど経ったころ、仕事の幅を広げるためにサッポロビールに転職した。そして、ビール部門の営業を経てワインのマーケティング部門に異動。そして、2度目のフランス留学を経てワイナリーの製造部門勤務となった。
「最終的にはワイン部門を志望していたので、希望が通った形でしたね。営業系から技術部門に行くことはほぼないという社風だったので、私のキャリアは相当珍しいものでした」。
ワインを売るために数多くの部署での経験を積んできた久野さんが目指しているのは、「つくり手と飲み手の架け橋となる」こと。
その夢の実現のために久野さん自身が必要だと思う経験を重ねていった結果、いつしか「グランポレール勝沼ワイナリーの工場長」になったというわけなのだ。
「フランスで勉強をしていた頃に強く感じていたのは、『ワインのつくり手と飲み手の言いたいことが伝わっていないことがある』という事実です。しかし不思議なことに、両者の思いの根源は同じようなものであることも多いのです。同じ思いでいるのに伝わらないのは、どちらにとってももったいないことですよね。つくり手と飲み手の思いをつなげるには、つくり手の技術的な部分を噛み砕いてお客様に伝えることが必要だと思ったのです。その為に技術的なことも学んでいるうちに、気づけばいつの間にか工場長になっていました」。
久野さんは、つくり手と消費者の翻訳者でありたいと話す。消費者の思いをすくい上げてつくり手に伝え、つくり手の『こういうワインが提供したい』という意思を消費者に伝えることが、久野さんの目指すものだ。
「幅広い分野で学んできたことを生かし、販売と製造の間に立って、ワイン造りをスムーズにすすめていけたらと思っています」。
久野さんが醸造に携わってから、10年近い歳月が経った。久野さんは自らの思いの実現に向け、これからもつくり手と飲み手の双方を幸せにするワインを醸し続ける。

『地域の特徴を生かすぶどう栽培』
続いては、グランポレール勝沼ワイナリーがおこなうぶどう栽培に迫っていこう。
畑のテロワールや栽培のポイント、品種選定のこだわりなどについて伺った。
▶︎長野2エリアの自社圃場 テロワールを生かして
グランポレールで取り扱うぶどうは、北海道、長野、山梨から供給。それぞれの地域が持つ特性が生きたぶどうで、ワイン造りをおこなっている。グランポレール勝沼ワイナリーではそのうち自社管理畑と単一畑のぶどうでつくるシングルヴィンヤードシリーズのワインを中心に作っている。
ここでは、自社管理畑の特徴やぶどう栽培のこだわりに焦点を当てていこう。4地域のうち、自社管理畑があるのは北海道と長野の2か所だ。今回はグランポレール勝沼ワイナリーのメインの自社管理畑である「長野」の畑を中心に紹介していきたい。
「グランポレールのコンセプトは、『その土地にあった品種を選んでワインを造ろう』というものです。長野県は、日本の中でも特に昼夜の寒暖差が大きい地域なので、フランス系品種を中心に品種選定しています」。
ほかの地域を見ると、北海道は酸が残りやすいため、ドイツ系のアロマティックな品種を栽培。山梨は土地に根付く甲州や甲斐ノワール。そして気温が高い岡山では、暑さに強いマスカット・オブ・アレキサンドリアやマスカット・ベーリーAを栽培している。
長野の自社管理畑は、大きくふたつのエリアに分かれている。ひとつは長野市にある「長野古里ぶどう園」、もうひとつは安曇郡池田町にある「安曇野池田ヴィンヤード」だ。それぞれのテロワールを見ていこう。

▶︎「柔らかさ」が強みの長野古里ぶどう園
長野古里ぶどう園のある長野市は、県の北部に位置する。千曲川氾濫によって堆積した平地に作られた畑であり、土質は砂や礫が主体だ。
そんな長野古里ぶどう園では、酸も残りつつ穏やかな味わいのぶどうが収穫できる。長野古里ぶどう園には、この場所ならではの特徴があるという。それは、11月に発生する「朝霧」だ。連日立ち込める朝霧は真っ白で深く濃い。しかし昼になると霧は嘘のように晴れ、乾いた風が吹く。
この現象を生み出しているのは、付近を流れる浅川と、畑のある場所の標高差だ。畑は浅川よりも高い場所にあるのだが、浅川と畑の間にある道が畑より高く、堤防の役割をしている。そのため、浅川から生まれた霧が畑に流れ込んで滞留し、畑がすっぽりと霧に覆われるのだ。
「朝霧が出て、昼には霧が晴れて乾く、まさに貴腐ワインの銘醸地『フランス・ソーテルヌ』と同じ気象現象が起こる場所なのです。長野古里ぶどう園は、自然に貴腐ぶどうができる、日本において非常に珍しい土地です。実際にグランポレール勝沼ワイナリーでは昔から、リースリングで貴腐ワインを造っています」。
穏やかさを生み出すぶどう栽培と、特有の「朝霧」。これらが長野古里ぶどう園ならではの特徴なのだ。
▶︎激しい寒暖差で生まれる「強さ」 安曇野池田ヴィンヤード
続いて紹介する「サッポロ安曇野池田ヴィンヤード」は、過去には桑畑として利用されていた経緯があり、ぶどう畑として利用するにあたって土壌改良が積極的におこなわれた場所だ。
安曇野池田ヴィンヤードは、信州ワインバレーのうち日本アルプスバレーに属する地域にある。標高560~630mの場所に広がっており、一枚の畑の中に大きな標高差がある急斜面の畑だ。傾斜は南西向きで、昼以降の日差しが強い。
土壌の性質も見てみよう。畑の土を掘り返すと、石がゴロゴロと出てくる。日本列島誕生に伴う地殻変動によって、山の瓦礫が積もってできた場所なのだという。
「安曇野池田のぶどうは、『強さ』を尊重しています。昼は低地からの温かい上昇気流があり、夜は冷たい北風で冷えるため昼夜の寒暖差が非常に激しい畑です。そのため、酸が残りやすく、かつ糖度も上がりやすくなっています。水分ストレスがかかりやすいためか、結果的に『ゴツめのワイン』になりやすい傾向があるのです。個性を生かしつつ、飲みやすさも追求しながら醸造しています」。
グランポレール勝沼ワイナリーは地域が持つ特有の強みを生かし、個性的なぶどうを育てているのだ。

▶︎長野で育てるぶどう品種 健全で成熟したぶどうを育てる管理方法
長野にあるそれぞれの自社畑で栽培している品種を見てみよう。
長野古里ぶどう園
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- メルロー
- シャルドネ
- リースリング
最初の栽培は1975年にスタートした。グランポレール勝沼ワイナリーにおいて最も歴史が古い自社畑だ。上記の品種が栽培される前までは、サッポロビールの前身である「大日本麦酒」のビール製造に使用する「ホップ」が試験栽培されていた。
安曇野池田ヴィンヤード
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- メルロー
- シラー
- ピノ・ノワール
- シャルドネ
- ソーヴィニヨン・ブラン
安曇野池田ヴィンヤードは比較的新しい畑である。取得は2009年で、ぶどうの植え付けが開始されたのは2010年から。最近だと2018年に植え付けられたぶどうもあり、まだまだ成長の途中だ。樹が成長し、安定した収量が確保できるようになってきたのは、品種にもよるが2018年頃からだという。今後のぶどうの変化も楽しみにしたい。
続いては、畑の管理方法を紹介していこう。
どちらの畑においても、「健全であること」をテーマに栽培されている点が共通している。病害虫被害が起こらないように丁寧に管理されているのだ。しかし、畑によって管理方法が異なっている点が興味深い。
長野古里ぶどう園の管理方法は、手作業が中心だ。草刈りや防除も、ぶどうの状態を見て決定される。ぶどうの樹単位での管理ができているのは、畑面積に比較して作業人数が多いから。長野古里ぶどう園は3haの畑を4人のメンバーで管理している。
一方の安曇野池田ヴィンヤードは、10haに対して6人で管理をおこなっている。人数が少ない分、多くの管理作業は機械化されているのが特徴だ。大規模農園であることから、機械を使って一斉に対応するほうが効率がよい。
収穫作業についても言及しよう。収穫期の判断は、糖度が十分に上がり、酸とのバランスがよい状態でおこなう。現場での判断はもちろんのこと、数値からの確認も欠かさない。成熟が近づくと果実を勝沼に送って糖と酸の数値を細かくチェックし、各数値を確認した上で収穫期を決める。収穫直前までは何度も数値を計測し、十分に成熟したかどうかを確かめるという。
「糖度や酸の数値から収穫期を決めるのが理想ですが、天候などの影響で前倒しで収穫しなくてはいけない状況もあります。常に畑のメンバーと議論しながら収穫期を決めていきます」。
科学的なアプローチと現場の判断というふたつの要素を合わせておこなう管理によって、高い品質のぶどうが栽培されているのだ。

『異なる産地を明確に表現したい グランポレール勝沼ワイナリーのワイン醸造』
グランポレール勝沼ワイナリーは、「ぶどうが育った産地が感じられるワイン」を目指している。
長野・北海道・山梨・岡山という4つの産地がひとつのブランドで体感できることは珍しい。醸造部門のワンチームが各地域のぶどうの特性や出来を見ながらワイン造りができることが、グランポレール勝沼ワイナリーの大きな強みだ。
産地ごとの特性の表現のため、また、消費者に満足してもらえるワイン造りのために、グランポレール勝沼ワイナリーがこだわっていることとは?ワイン醸造について詳しく伺った。
▶︎最も大切なのは「健全性」 産地の個性を表現するために
グランポレール勝沼ワイナリーがワイン造り全体でもっとも大切にしているのは、「健全性」だ。つくり手は自らに厳しい基準を課し、ワインの健全性を遵守する。
「健全性を守る作業」について、具体的な例を挙げてみよう。酸素との接触を適切に管理すること、ぶどうにストレスを与えない温度管理、醸造設備・醸造器具の徹底的な清掃などが、健全性を守る作業に該当する。
健全性の確保は、安心安全な製品づくりの基本になるものだ。衛生管理目的だけでなく「美味しいワイン」造りにもつながる。健全な醸造ができれば、酵母や微生物に余計なストレスを与えることなく、ぶどうが持つ力や性質をストレートに表現することが可能になる。グランポレール勝沼ワイナリーが目指す「産地の表現」を果たすことができるのだ。
久野さんは健全性とワイン醸造の関係について、次のように話す。
「ワインは外部からの環境によって、素直に発酵しなくなることも多々あります。醸造工程すべてにおいて健全な状態を保つことが、ワインの醸造チームがおこなえる最低限かつ最大の仕事なのです。基本をしっかりとおこなって健全性を保てば、産地やヴィンテージ特有の味わいを自然に引き出すことができると思っています」。
醸造の健全性を最重要視するグランポレール勝沼ワイナリーのスタンスは、長く引き継がれているものだという。
今や健全性への意識はグランポレール勝沼ワイナリー全体にしっかりと浸透しており、健全性への厳しい風土が勝沼ワイナリーにおけるひとつの「特徴」になっている。
繁忙期であるワインの仕込み中、普通は「果汁が周囲に飛んだり」「器具にぶどうがこびりついていたり」するものだ。汚染とまではいかなくとも、そこには何かしらのワインとは別の匂いが発生することもあるだろう。
だが、グランポレール勝沼ワイナリーの醸造設備からは、健全なワインとぶどうの香り以外はいっさい感じられない。フランス留学経験もあり、国内外の数多くのワイナリーを知る久野さんでも、「こんなに清潔なワイナリーは見たことがない」と言う。
「グランポレール勝沼ワイナリーの醸造設備の清潔さは、機械的に消毒された工業的なきれいさではありません。あくまでも『人が努力を保っているからこそ実現できているきれいさ』なのです。たとえば、樽にワインを移し替える作業ひとつをとっても、きれいに管理する努力がうかがえます。ワインを1滴もこぼさず、シミひとつけないのです。そういった日頃の態度に、健全性への深いこだわりがあらわれています」。
ぶどうを素直にワインにするために人ができることは、醸造所の健全性を保つこと。メンバーそれぞれが、その重要性を体の芯まで理解しているからこそ、産地の個性を表現できる純真無垢なワインが醸せるのだろう。

▶︎「記憶をなくすほど大変」な仕込み作業
久野さんに醸造の様子を伺うと「毎年記憶をなくすほど大変です」と苦笑する。
「どんなによいぶどうが来たとしても、タンクにすべて入り切らないことがあるのです。それでも新鮮なうちに発酵させたいので、普段使っていない移動可能な小型タンクも運び出して仕込みをすすめました。2020年は北海道の収量が例年の1.5倍にもなったので、醸造のスケジュール管理が本当に大変でしたね」。
どんなに忙しい仕込の場面でも、醸造メンバーは細かな視点でワインを見つめる。醸造担当者は「技術者」であり、個々の細かな部分に注目していることが多いという。
「根っからの技術者なので、視線がそれぞれの細部まで行き届いていると感じます。会話の内容も『今年の出来』のような広い範囲の話ではなく『今日仕込みに使ったこのタンクの、この品種の様子』についてといった話が大部分です。ワインが生徒だとすると、先生たちが学年全体ではなく、生徒ひとりひとりについて話をしているイメージでしょうか。常にタンク単体の状態を細かく観察し、分析してメンバー間で情報共有しています」。

▶︎あらゆる人とシーンに対応できるラインナップが魅力
グランポレールの製品は、およそ30銘柄が展開されている。ひとつのブランドであらゆる消費者に対応できる点が、強みのひとつになっている。
「スーパーでワインを買おうという気軽なワインファンや、年に1回くらいしかワインを飲まないという方、普段からワインを嗜むワインラバーや日本ワイン好きのお客様まで、幅広く満足させられるラインナップがあります。ワインファン以外にも客層が広いのは、ビールも造っているサッポロならではの強みかもしれませんね」。
幅広い消費者の好みに合致するワインを提供できると同時に、「個人のあらゆるニーズを満たせる力」を兼ね備える点も見逃せない。
デイリーワイン、週末の夜用、記念日用。または、普段の食事に合わせるワイン、ホームパーティー用のワインなど。幅広いシーンに合うように、グランポレール全体のイメージが形造られているのだ。
さらに、2023年6月からは現行ワインのラインナップを一新。自社および契約栽培農家のぶどうのみを使ったハイレンジの「シングルヴィンヤードシリーズ」や、大きな産地のまとまりで醸すミドルレンジの「キャラクターシリーズ」。そして、気軽に楽しめるブレンドワインが中心の「スタンダードシリーズ」の3種類だ。食べる料理や気分に合わせてワインを選ぶ楽しさを、ぜひ味わってみてほしい。

▶︎シングルヴィンヤードシリーズのおすすめワイン
シングルヴィンヤードシリーズから、久野さんおすすめのワインを紹介していただいた。
「グランポレール 安曇野池田ソーヴィニヨン・ブラン<薫るヴェール>」と「グランポレール 安曇野池田 シラー」だ。
まずはソーヴィニヨン・ブランから見ていこう。「グランポレール 安曇野池田ソーヴィニヨン・ブラン<薫るヴェール>」は、2021年から登場した銘柄だ。「薫る」と名付けられている通り、香りの強さが特徴となっている。工夫と試行錯誤の結果、ソーヴィニヨン・ブランの特徴的な香りを出すことができた。
「安曇野池田のソーヴィニヨン・ブランは、長い間思い描く香りがはっきりと出ず、悩んだ期間がありました。転機となったのは2021年です。造り方を劇的に変えて、よい味と香りを出すことが出来たのです。フランス・ボルドーから返ってきたメンバーの意見を積極的に取り入れて実践した結果でした」。
ソーヴィニヨン・ブランの香りを引き出すための勝負は、畑の段階から始まる。ぶどうには「香り物質の前駆体」と呼ばれる物質が含まれており、前駆体が発酵によって香り物質に変化するのだ。つまりぶどうに前駆体を増やさない限り、ワインになったときに最終的な香りが残らないのだ。
そこで、前駆体を残すための栽培方法を採用。酸化によっても前駆体は減ってしまうので、醸造の段階でも極力酸化させない管理をおこなう。味わいの厚みのことも考えて一部にのみ樽を使用し、最終的にブレンドする手間をかけて造り上げた。
「日本のソーヴィニヨン・ブランの中でも、特にはっきりとした香りがでた味わいになったと自負しています。さらに、安曇野池田ならではの力強さも感じることができますよ」。
グランポレール勝沼ワイナリーの努力と工夫が詰まった渾身の1本。ぜひ豊かな香りを感じてほしい。
続くおすすめワイン、「グランポレール 安曇野池田 シラー」の紹介に移りたい。安曇野池田のシラーは、スパイシーな香りが強く、かつフルーティー。骨格のある酸が残りつつアルコールのボリューム感もある端正な味わいだ。久野さんは、安曇野池田のシラーを「カリッとしたシラー」と表現する。
「安曇野池田の土地とシラーの相性がよいのでしょう。締まりのよいシャープなシラーになります。海外のシラーと比べても特徴的で、『日本のシラー』が楽しめる銘柄になっていますね」。
日本のシラーのキーワードは「冷涼感」。輪郭がはっきりとしているのが特徴だ。シラーの銘醸地、フランス・ローヌと比較しても違いが顕著だという。背筋が伸びて引き締まった、「かっこいい」シラー。安曇野池田ならではのシラーを楽しんでみてはいかがだろうか。

▶︎キャラクターシリーズのおすすめは、樽発酵の甲州
続いてのおすすめは、キャラクターシリーズから「山梨 甲州<樽発酵>」だ。山梨で収穫され出荷組合に集められた甲州のうち、糖度の数値と試食によって厳選された果実だけで醸した。
「樽発酵甲州、最大の特徴は『大きさ』です。甲州はさっぱりしたタイプのワインが多い中、『山梨 甲州<樽発酵>』は圧倒的なボリューム感があります。樽の厚みがありつつも甲州由来の香りが負けておらず、あらゆる要素に『大きさ』を感じさせるワインです」。
ボリューム満点の甲州を生み出す秘訣は、半年程度寝かせる「樽」。そして香りのよいロットと味のよいロットのブレンドが織りなす妙だ。
おすすめのペアリングは、なんと「とり天」だという。「それくらいボリュームのあるものと合わせてほしいですね」と、久野さん。
「甲州は和食との相性はよいものの、繊細なメニューですと「山梨 甲州<樽発酵>」の方が強くなってしまうかもしれません。タルタルソースをかけたチキン南蛮でもしっくりくるくらいのボリューム感ですよ。ぜひ、今までにない甲州を味わってみてくださいね」。

『グランポレール勝沼ワイナリーが描く、日本ワインの未来』
最後のテーマに移ろう。最後は、ワイナリーが掲げる将来の目標と、つくり手が考える日本ワインについての思いを深掘りする。
グランポレール勝沼ワイナリーは今後どのようなワインを醸し、どんな思いでワイン醸造と向きあっていくのだろうか。
▶︎今後のワイン造り 「産地の表現」を今まで以上に突き詰めて
「今までもグランポレール勝沼ワイナリーでは、ぶどう産地の表現をテーマにワイン造りをおこなってきました。これからは北海道や長野といった『地方』の表現からさらに絞り込んで、地方の中の『地域』の表現をしていきたいです。そして、さらに畑の中の『区画』が持つ特性にクローズアップしたワイン造りも目指していきたいと思っています」。
グランポレール勝沼ワイナリーが「産地表現の次の段階」へと進むきっかけとなったのは、北海道圃場の新エリア「北斗」でのぶどう栽培がスタートしたことにある。今までは、北海道「余市」のぶどうのみを使用してきたが、2023年6月6日に500本限定で「北斗シャルドネ」を発売。本格リリースは2024年以降を予定している。「北海道のぶどうのワイン」というだけでなく、「余市のワイン」「北斗のワイン」の違いが如実に感じられるワイン造りが理想だ。
「土地の個性表現をさらに細密に、極めていきたいです」という久野さんの言葉は力強く、新しいワイン造りへのステップに進むことへの決意を感じさせる。

▶︎久野さんが思う「日本ワイン」のこれから
最後に伺ったのは、日本ワインが今後どうなっていくかという問いについて。
グランポレール勝沼ワイナリーの工場長として久野さんが考える「日本ワインの未来」についてお話いただいた。久野さんの言葉から見えたのは、日本ワインを盛り上げようという情熱と、日本の食文化への信頼だった。
「『日本の食事と日本ワインは絶対に合う』ということをまずお伝えしたいです。さらに、和食という枠組みにとらわれず、日本で食べることのできる食全般と合わせて楽しんでほしいのです。日本の食材や調味料を使った洋食、中華などには、本場の料理とは違った『日本特有の』テイストがあります。日本のワインにはそういった日本特有のテイストが自然と含まれていますので、日本で作られたあらゆる料理に日本ワインはマッチするのです」。
ステーキを例にしよう。ステーキといえば重い赤ワインとペアリングするというセオリーがある。そのため、ボルドーの赤ワインや牛肉王国であるアルゼンチンの赤ワインを合わせたくなるかもしれない。
しかし繊細な赤身や、旨味やまろやかな脂身が特徴の国産牛であれば、「日本の赤ワイン」を合わせてみることで新しい発見があるのではないだろうか。
「さまざまな食文化を自国の素材や調理法でアレンジしながら、食文化は発展しています。ワインも同じで、日本素材の料理に日本ワインを合わせる楽しみ方が広まれば、より発展していくものではないでしょうか」。
グランポレール勝沼ワイナリーのつくり手、久野さんの願いはシンプルだ。「みんなで日本ワインの品質を高めあっていきたい」。ワインを愛する人間としての純粋な願いが、日本ワインの未来をより発展させていくのだろう。
『まとめ』
グランポレール勝沼ワイナリーは産地の特性を生かしたワイン造りをおこなうワイナリーだ。「健全性」という共通のコンセプトでぶどうと向き合うことで、土地にしかない個性を浮き彫りにし、ワインに投影する。
日本ワインの品質を高めるために、日本にあるワイナリー同士で多様性を認め合いながら切磋琢磨していきたいと話してくれた久野さん。
ワイナリー同士が「お客様に喜んでいただきたい」という軸でつながり、お互いのよい部分を吸収しつつ成長していけたらと話す久野さんの視野は広く、日本ワインに向ける眼差しは愛情に満ちている。
グランポレール勝沼ワイナリーは日本ワインの発展のためにできることを本気で考え、ワイン造りに真摯に向き合っているワイナリーだ。グランポレール勝沼ワイナリーを訪れたときにはワインを楽しむだけでなく、ワイナリーツアーにも参加して、つくり手の情熱に触れてみてほしい。

基本情報
| 名称 | グランポレール勝沼ワイナリー |
| 所在地 | 〒409-1305 山梨県甲州市勝沼町綿塚577 |
| アクセス | https://www.sapporobeer.jp/brewery/katsunuma/access/ |
| HP | https://www.sapporobeer.jp/brewery/katsunuma/ |