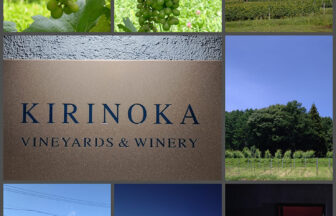千葉県初の都市型ワイナリーである「船橋コックワイナリー」が船橋市に誕生したのは、2021年のこと。閑静な住宅街の一角で、手作業中心のワイン醸造をおこなっている。
船橋コックワイナリーを設立したのは、『図解 ワイン一年生』の著者、小久保尊さん。千葉県船橋市にある、肉とチーズとワインのバル「コックダイナー」のオーナーでもある。
コロナ禍でレストラン運営が思うようにできない中、空いた時間をチャンスと捉え、ワイナリーをスタートした。「ワインをもっと身近に感じてほしい」という思いからだった。
船橋コックワイナリーでは、農家から買い付けたぶどうを電動機械を極力使わずに醸造している。手作業中心なのは、ワイナリーがあるのが住宅地で、大きな音の出る機械が使えないためだ。だが、手作りならではの素朴な味わいを味方に付けて強みとした。
2021年ヴィンテージでは、赤ワインや白ワイン、ロゼ、オレンジワインなど9種類を展開。甲州やブラッククイーン、マスカット・ベーリーA、デラウエアなどの品種を扱った。
船橋コックワイナリーが目指すのは、「日本の家庭料理に合う、優しい味わいのワイン」。街中で造るワインならではの、できたてのフレッシュ感を重視する。
今回は小久保さんに、2022年の船橋コックワイナリーについてのお話を伺った。ぜひ最後までお読みいただきたい。
『2022年の船橋コックワイナリー』
バルの経営に加え、ワイナリー運営も兼任している小久保さん。特に忙しくなるのは、9~11月の醸造シーズンだ。
ワイナリー見学会や醸造体験も始まったため、2022年はスタッフを増やして繁忙期を乗り切った。
▶︎ワイナリー見学会をスタート
醸造作業がピークの時期の小久保さんの1日はどんな様子だったのか。
「朝はワインの仕込みに入って、午後からはバルで開店準備をする日々でした。スタッフと協力して作業をおこなったので労働時間はそれほど長くありませんでしたが、繁忙期には、休みは取れなかったですね」。
また、ワイナリー見学会もスタートさせた船橋コックワイナリー。予約制の見学会は、毎週日曜日に開催している。
ワイナリー見学会では、小久保さんが自ら醸造用機材や醸造工程について説明を担当する。説明した後は、ワイナリーの2階に移動して、ワインのテイスティングタイムとなる。
都市部にあるワイナリーのため、公共交通機関を使って気軽に行けるのも、船橋コックワイナリーの魅力のひとつだ。
ワイナリー見学会に来る人の中には、見学後に小久保さんの経営するバルでワインと食事を楽しむ人も多い。ワイナリー見学会の予約が入れば、見学会前にバルの営業準備を済ませ、見学後に営業を始めるという小久保さん。忙しささえも楽しみに変えているようだ。
また、2022年の仕込み時期には、バルの常連客や知り合いの飲食店の人に、手伝いも兼ねた醸造体験をしてもらったそうだ。
「2023年からは一般の方々にも醸造体験をしていただこうと考えています。SNSなどで告知しますので、興味がある方はぜひチェックしてください」。

▶︎ワインをもっと身近に感じてもらいたい
小久保さんは2015年に「図解 ワイン一年生」という書籍を出版し、大ヒット。そもそもワインに興味を持ったきっかけはなんだったのか?改めて伺ってみた。
「大学生のときに、ソムリエのいる飲食店で働き始めたのが、ワインに触れた初めての機会でしたね」と、振り返る。だが、当時は取り立ててワインだけが好きだったわけではなく、料理とお酒全般に興味があったそうだ。
ワインの本を出版したのは、ワインを扱う店を自ら経営し始めた後のことだ。書籍の出版も、ワイナリーの設立理由と同様に、「ワインをもっと身近に感じてもらいたい」という思いからだった。
その後も小久保さんはワインへの強い思いを持ち続け、コロナ禍を機にワイナリーの設立に至った。そんな思いで設立された船橋コックワイナリー。これからワインに触れてみたいと思っている人にもぴったりのおでかけスポットだろう。

『2022年のワイン醸造』
船橋コックワイナリーでは、ファーストヴィンテージだった2021年には、主に長野県や山形県から買い付けたぶどうを使ってワインを醸造した。
しかし、2022年はぶどうの仕入れ先をすべて東北に変更。多くは山形県から、一部を岩手県から仕入れたという。
▶︎思いどおりのワイン造り
醸造に使用するぶどうを東北に絞ったのには、もちろん理由がある。2021年に、ぶどう農家をまとめるブローカーから購入したぶどうの質がとても高かったからだ。そのブローカーが扱っている主な仕入れ先が、東北の農家だったのだ。そして、購入先を絞ったことで、扱う品種も大きく変更した。
「2021年から引き続き仕入れているのはデラウエアですね。2022年は、キャンベルとスチューベン、ナイアガラ、メルローも購入しました」。
特にナイアガラは、以前から小久保さんが「ワインを造ってみたいぶどう」として挙げていた品種だ。2022年に扱った品種は、大半が小久保さんの希望に沿っている。
2021年はワイナリーの醸造免許が下りたのが9月末だったため、そこから醸造可能なぶどうをかき集めたという経緯がある。
「2021年はギリギリのスケジュールで動いていたため、醸造したい品種を選ぶ余裕がまったくなかったのです。また、醸造自体も初めての取り組みで、長期間留守にできない私の代わりに、当時のスタッフのひとりがほかのワイナリーにワイン醸造を学びに行ってくれたので、そのスタッフ主導で仕込みました。その点、2022年は品種選びも醸造も思い通りにできたので満足です」。

▶︎日本の家庭料理に合うワインを
小久保さんがワインにしたいと選んだ品種は、主にヴィティス・ラブルスカ種だ。ラブルスカ種とは北アメリカ大陸にルールを持つ品種。一方、ヨーロッパ原産でワイン用として扱われるぶどうは、ヴィティス・ヴィニフェラ種と呼ばれている。
小久保さんがラブルスカ種にこだわるのは、「日本の家庭料理に合うワインを造りたい」から。生食用として広く流通し、日本での栽培実績も多い品種で造るワインこそ、日本の家庭料理に合うと考えているのだ。
ただし、2022年はナイアガラで晩腐病が発生し、購入を想定していた量が入荷しなかったため、メルローも追加で購入した。メルローはヴィティス・ヴィニフェラ種ではあるが、試してみることにしたそうだ。
『品種ごとの個性がしっかり感じられるワイン』
船橋コックワイナリーの2022年のワインの出来栄えは、2021年のワインを上回ると話してくれた小久保さん。品種特性を生かせるような仕込みをおこない、思い描く味わいを表現できた。
どれもフレッシュな早飲みタイプで、それぞれの個性がしっかり感じられるワインになった自信作だ。
「私自身が好きな味わいのワインをイメージしながら醸造しました。我ながらうまくいったと思いますよ。お客様からの評判も上々です」。
2022年ヴィンテージワインのうち、いくつかの銘柄について詳しく紹介しよう。
▶︎2022年ヴィンテージのワイン紹介
デラウエアは、白ワインとオレンジワインの2種類を醸造した。白ワインの方がよりフレッシュで、果実をそのままかじったような味わい。種と皮を一緒に醸したオレンジワインは、味に深みが増してまろやかな仕上がりになった。
また、キャンベルでは、赤ワインとロゼワインを造った。キャンベル特有の華やかでチャーミングな、いちごのような香りが好評なのだとか。
「特にロゼは、普段ワインを飲まない人にも好評で、『カクテルみたいな味わいだね』と言われます」。
キャンベルのワインは「NAGOMI キャンベル」という銘柄で、発色のよい鮮やかなピンク色もポイントだ。酸味もさほど強くなく、ワイン初心者でも飲みやすい。スパイスの効いた料理に合わせるのがおすすめだ。
そしてナイアガラは、「君に晩腐」というネーミングが秀逸な1本。晩腐病をサバイブしたという思いを込めてつけた名前だ。

▶︎スチューベンは特におすすめ
2022年ヴィンテージのスチューベンの赤ワインとロゼワインは、小久保さんの自信作。「キャトられスチューベン」という名前で、UFOにワインが連れ去られるエチケットも個性的だ。
「スチューベンのワインが美味しく仕上がったので、宇宙人も欲しがる美味しさだと思って名前とエチケットを考えました」。
実は2022年のスチューベンの赤ワインは、初めて無添加で醸造したワイン。天然酵母で発酵させ、亜硫酸も不使用だ。
失敗の可能性を考慮して、小さめのタンクで少量生産をした。半分はぶどうを房ごと発酵する醸造技術を採用。残り半分を除梗破砕してタンクに加えて一緒に仕込み、納得の味わいとなった。
「とてもよい状態のスチューベンが届いたので、力強い味わいを生かして醸造したいと思い、天然酵母で発酵させることにしたのです。自分らしさが全面に出たワインになりました」と振り返る。大きな失敗もなく、180本のワインが誕生した。
スチューベン自体に、野菜のニュアンスを感じるという小久保さん。ほのかにタンニンが感じられる味わいのワインだということもあり、筑前煮のような根菜系の煮物やきんぴらなどに合わせるのがおすすめだ。
スチューベンのロゼワインは2週間ほど醸して淡い色合いを出し、ゆったりと飲めるワインに仕上がった。ロゼはフレッシュな野菜と合わせてほしいということなので、トマトとモッツァレラチーズのサラダ「カプレーゼ」などとペアリングしてみたい。

▶︎メルローはロゼのスパークリングワインに
さて、ラブルスカ種ではないメルローは、どのようなワインに仕上がったのかが気になる人もいるかもしれない。
「メルローでは、ロゼのスパークリングワインを醸造しました。スパークリングワインは初挑戦でしたが、メルロー特有の気の根っこのようなニュアンスが感じられる、よい仕上がりになりそうです」。
ヴィティス・ヴィニフェラ種のぶどうについて感想を尋ねてみると、「手動で搾るバスケットプレスを使用していますが、ラブルスカ種と違って、メルローは搾りやすかったのが印象的でした。ラブルスカ種はペクチンが多くて、ドロドロして搾りにくいんですよね」と苦笑い。手作業ならではの苦労を垣間見ることができるエピソードだ。
微発泡タイプでにごりがあるタイプの、メルローのスパークリングワインの発売は6月頃を予定している。気になった方は、ぜひ公式Webサイトをチェックしてみてほしい。
『都市型ワイナリーならではのワイン造り』
船橋コックワイナリーは、近くに系列のバルもある都市型ワイナリー。造りたてのワインをすぐに提供できるのが特徴だ。
フレッシュなワインを味わうことができ、ワイナリーに興味がある人が足を運びやすいなど、飲み手にとっては都市型ワイナリーならではの利点がいくつもある。
都市でワインを造ることに込めている思いや、都市型ワイナリーだからこその大変さを伺った。
▶︎ぶどうに感謝して、「無駄にしない」を実践
ワインを醸造するとき、小久保さんがいつも感じているのが「ぶどうに対する感謝」だ。
「『農家さんが今年もぶどうを作ってくれたから、自分たちはワインを造ることができる』という思いがすごく強いですね。そのため、ぶどうの搾りかすまで、余すことなく無駄にしないようにと考えています」。
自社畑を持たない、都市型ワイナリーならではの考え方だろう。
例えば「UMAMIキャンベル」は、「ぶどうを無駄にしない」という考え方を突き詰めたワインのひとつ。まず、キャンベルのロゼの搾りかすを、キャンベルの赤ワインに投入し、色味やうま味をアップさせるために利用した。
そのほか、搾りかすで香りや色をつけたクラフトビールの製造を、千葉県松戸市にある「松戸ビール」に依頼。2022年に造ったクラフトビールはすでに完売し、2023年秋にもまた造る予定だ。
また、ほかにも肥料として二次利用してもらったり、燃やした灰を焼き物の釉薬(ゆうやく)として使ってもらう試みもおこなったそうだ。
自然豊かな東北で栽培されたぶどうが都市部にやってきて、美味しいワインとなる。そして、搾りかすまで余すことなく活用されることは、ぶどうの栽培農家にとってもきっと嬉しいことに違いない。

▶︎「千葉ワインフェス」開催を目指す
今、小久保さんが開催したいと考えているのは「千葉ワインフェス」だ。
「千葉県にある4つのワイナリーが合同で、2023年5月に試飲会を開催します。また、2023年から2024年にかけては千葉にワイナリーが2件ほど増える予定です。近い将来、千葉ワインを盛り上げるために、『千葉ワインフェス』を開催したいですね」。
ワイナリー同士で話し合い、開催に向けての計画が進んでいるそうだ。2024年以降のフェス開催を目標としている。2023年は船橋コックワイナリーのワインをもっと多くの人に知ってもらうため、祭事への出店を積極的におこなっていく予定だ。
『まとめ』
2022年、小久保さんが「造ってみたい」と思い描いていたワインはいったん完成した。また、2023年ヴィンテージにはさらにブラッシュアップさせ、もっと美味しいワインを作ることができると感じているそうだ。
船橋コックワイナリーのワインを、地元・船橋の人たちに楽しんでほしいと考えている小久保さん。
「船橋はなんでもある街ですが、実は名産品といえるものは少ないので、船橋コックワイナリーのワインを船橋土産として選んでもらいたいですね」。
造りたての美味しさが味わえるフレッシュなワインを地元で造っているということに、魅力を感じる船橋の人はたくさんいるだろう。今後、さらに地域に根差したワイナリーとして発展していく船橋コックワイナリーを応援したい。

基本情報
| 名称 | FUNABASHI COQ WINERY |
| 所在地 | 〒2730004 千葉県船橋市南本町36-9 |
| アクセス | JR船橋駅から徒歩16分 |
| HP | https://fcw.theshop.jp/ |