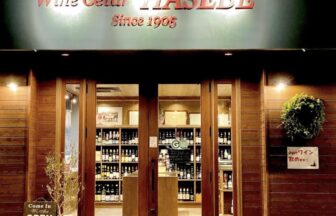キリンホールディングス株式会社のグループ会社であり、ワインを中心とした酒類の製造・販売をおこなっているメルシャン株式会社。
「日本を世界の銘醸地に」というヴィジョンを掲げ、日本ワインを牽引し続けるメルシャンの日本ワインブランドが、「シャトー・メルシャン」である。
山梨県甲州市の「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」、長野県塩尻市の「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー」、長野県上田市の「シャトー・メルシャン 椀子(まりこ)ワイナリー」という3つのワイナリーから生まれたワインは、それぞれの土地のテロワールや歴史、地域との絆を映し出す。
そんなシャトー・メルシャンが有するワインに関する幅広い知見を生かすべく、新たな日本ワイン産業振興の取り組みとして、スタートアップワイナリーへのコンサルティング事業を開始したメルシャン。栽培や醸造技術に課題を抱えているスタートアップワイナリーに対して、多方面から手厚く具体的な支援をおこなっている。
今回は、開始から3年弱が経過したコンサルティング事業について、コンサルティング事業を担当する経営企画部の常駐メンバーである、シニア・ワインメーカーの藤野勝久さんと田村隆幸さんにお話を伺った。
『ワイナリー向けコンサルティング事業』
まずは、メルシャンがコンサルティング事業に乗り出した経緯について紹介したい。田村さんから詳しい背景を説明いただいた。
メルシャンがワイナリーへのサポートサービスを試験的に開始したのは2021年のこと。新たな日本ワイン産業振興の取り組みとして、スタートアップワイナリーへのコンサルティング事業を計画したのだ。シャトー・メルシャンでのワイン造りの知見を生かして、持続可能な日本ワイン産業を目指す新事業だ。
▶︎新事業をスタートした背景
メルシャンが新事業をスタートした背景には、日本においてワイナリー数が急増していることがあった。田村さんはワイナリー数の増加を評価する。だが一方で、スタートアップワイナリーの多くは栽培・醸造技術、品質面でさまざまな課題を抱えていたのだ。
「新規ワイナリーが増えるにつれて、栽培や醸造をする上での困りごとがあるという話が聞こえてくるようになりました。ワイン造りへの情熱を抱いて参入しても、学ぶ機会を得ることは決して簡単ではありません。また、座学中心の知識だけでは、現場ですぐに役立てることは難しいという声も多かったですね」。
スタートアップワイナリーに必要なのは、基本に則った正しいワイン造りの知識と、現場で生かせる経験だ。自社が運営する3つのワイナリーで培ってきた知識と経験を提供すれば、新規参入者の苦労や負担を軽減できるのではないかとメルシャンは考えたのだ。
そこで、145年にわたるワイン造りの経験と経験豊富な人財という資産を活用して、日本ワイン産業における課題を解決するためにスタートアップワイナリーへのコンサルティング事業を2022年9月に開始したのだ。
田村さんは、コンサル事業を通じて、メルシャンが掲げる「日本を世界の銘醸地に」というヴィジョンを実現したいと話す。
「銘醸地として認識されるためには、高い品質のワインを生産するワイナリーが一定数存在し、そのワインが一定の品質レベルを形成することが必要です。1社だけが卓越したワインを生産しても、銘醸地とは言えないでしょう。メルシャンは、日本でのワイン生産地形成に貢献するDNAを持っています。ワイナリーへの助言をおこなうコンサルティング事業を通じて新規ワイナリーの立ち上げを支援し、ワイン産地形成を実現することが、本事業の意義と目標なのです」。

▶︎ワイナリーからの声を受けて
新規参入者からの声として最も多いのが、「相談できる人がいない」という悩みだった。山梨や長野、北海道など、ワイン用ぶどうの栽培が盛んでワイナリーが多い地域がある一方で、県内に数件しかワイナリーがないエリアも存在する。
「ワイナリーが多いエリアでは横のつながりがあるため、困った時に相談できる人が身近にいます。しかし、ワイン造りが始まったばかりの場所では、周囲に相談できる人が全くいないことも珍しくありません」。
周囲にワイン用ぶどうの栽培経験者がいない場合、新規参入者が相談する先は「生食用ぶどうの栽培農家」になることが多い。だが、生食用と醸造用の栽培では、気をつけるべき点が大きく異なる。ハウス栽培が基本の生食用と、露地栽培が基本のワイン用ぶどうを同じように管理することは難しく、生食用の栽培セオリーに従っても上手くいかないケースが出てくる。
「生食用ぶどうの栽培農家さんから学べることも、非常に沢山あります。しかし、ワイン用ぶどうの栽培ならではの知識と経験がなければ解決できない問題が多いのも事実です」。
さらに、相談できる人がいないことは、2次的な問題を引き起こす可能性があると田村さんと藤野さんは指摘する。「困っていることや改善すべき点があること自体に、そもそも気づいていない」という問題である。
実際、田村さんと藤野さんが関わった案件でも、栽培や醸造の手順が原則から逸れていたり、チグハグなことをしていたりというケースが複数あったそうだ。だが、孤軍奮闘していて指摘してくれる人がいない場合、間違いをおかしていることに気づけないのだ。

▶︎コンサルティングサービス概要
メルシャンが提供するコンサルティング事業では、ワイン用ぶどうの栽培とワイン醸造、生産に関する技術的なサポートを実施。さらに、将来的にはマーケティングや販売に関する幅広いコンサルティングなども含め、適切な支援を提供する計画である。ワイナリーが抱える悩みに応じて、柔軟にカスタマイズしているというサービスの概要を紹介しよう。
コンサルティングサービスの利用者が最も気軽に利用できるのが、「オンライン相談窓口」だ。メルシャンのサポートメンバーに、オンラインでいつでもワイン造りの悩みを相談できる。「病気の対応方法」「芽かきのコツ」など、畑で撮影した画像と共にチャットで質問すると、具体的な対応方法やアドバイスを受けられる。
チャットでのやりとりだけでは解決が難しい場合は、オンラインミーティングで話し合うことも可能だ。さらに、相談内容によっては、メルシャンのサポートメンバーが現地に足を運ぶこともある。畑での栽培の様子や病気の状況を見た上で今後の方針を検討するのだ。
「チームのメンバーごとに専門分野があるので、最適な担当者を現地に派遣してサポートをおこないます。畑を見れば、より具体的なアドバイスや細かいチェックができますね」。
サポートする範囲は、相談内容に応じてフレキシブルに対応可能だ。樹形を整える方法などの具体的な指導や、過去の防除歴を確認して今年の防除計画をアドバイスすることもある。また、収穫時期に現場に張り付いて、収穫から破砕・仕込みまでを全て指導したケースもあった。最終的なワイン造りの方向性は各ワイナリーが決定しているが、要望に応じてワイン造りの方向性をガイドすることもあるという。
さらに、出来上がったワインの品質チェックにも対応。現地での対応はもちろん、メルシャンにサンプルを送付してさらに詳しい分析を受けることも可能だ。
「メルシャンが保有している分析機械を使います。小規模ワイナリーでは難しい詳細な分析をおこなえるため、ワイン造りの参考にしていただけます」。
分析結果を元にして、ボトリングするまでに必要な安定化の処理方法などの具体的なアドバイスも提供している。
あらゆる角度からワイナリーを全面サポートする、メルシャンのコンサルティングサービス。今後もオンラインと現地指導を併用しながら、質問に対応できる体制を整えていく。

▶︎教えることが自身の成長につながる
メルシャンが提供しているスタートアップワイナリーへのコンサルティング事業で、オンラインサポート対応を担当している常駐メンバーは、経営企画部に所属する田村さん、藤野さんを含む3名だ。また、シャトー・メルシャンで働く現役社員も、必要に応じて対応にまわる。
さらに、シャトー・メルシャンのOBにも事業への協力を仰いでいる。社員として活躍していた時から兼業農家だったメンバーも多く、現在もワインをよく知る現役農家としてぶどう栽培に携わっているベテラン揃いだ。
「メルシャンが持つ幅広い知識と経験を総動員して、日本全国のワイナリーをサポートできる環境を整えています。コンサルティング事業は、教える側にとっても成長の機会になるはずです。私自身もかつて、教えることで成長した経験があります」と、田村さん。
田村さんは、教えることで自身を成長させる経験を、メルシャンの現役メンバーにも味わってほしいと考えている。コンサルティング事業は、新規ワイナリーの助けになるだけでなく、メルシャンの人材のレベルアップにも貢献できる取り組みなのだ。

▶︎担当コンサルタント紹介
ここで、コンサルティング事業を担当するコンサルタントのうち、今回インタビューに対応いただいた藤野さんと田村さんを改めて紹介しておきたい。
まず、藤野さんは、1979年にメルシャン株式会社に入社。「日本ワインの父」と称される浅井昭吾(ペンネーム:麻井宇介)氏が工場長を務めていたメルシャン藤沢工場に配属され、ワイン造りの道に入った。その後、ボルドー駐在などを経て、多数のコンクール審査員としても活躍。日本ワイナリー協会顧問、葡萄酒技術研究会エノログ部会長なども務める。
藤野さんがワイン造りに対して抱いてきた信念には、浅井さんから受け継いだ精神が一貫して生き続けているという。
「浅井さんは温厚な人柄の方でした。しかし、ものづくりに対してはシビアで、特にお酒の品質に関しては非常に厳しかったですね」と、当時を振り返る。
「実は入社時、私は別の分野で活躍することを希望していました。偶然ワイン造りの現場に配属されたのですが、今振り返ると、それが全ての幸せを運んできてくれたのだと感謝しています。ワインを通して世界中の人たちと出会い、現在もなお活躍できる仕事に出会えたことに感謝しています。ワインは私の人生の全てであり、ワインのお陰で本当に幸せです」。
続いて、田村さんは1999年にメルシャン株式会社に入社し、ワインの基礎研究と商品開発に従事。海外での醸造や原料ぶどう調達業務、自社管理畑の拡大を担当し、勝沼ワイナリー長、椀子ワイナリー長を歴任した。
田村さんがワインと出会ってお酒の楽しさを知ったのは、学生時代のアルバイトでバーテンダーをした時のこと。大学2年の夏休みにドイツで夏休みを過ごした際には、ワイン造りに興味を持った。そして、田村さんの将来を決定付けたのは、フランス・モンペリエに留学した際の出来事だった。
「『フランス人が新世界にワイン造りを教えた』と威張っていた醸造科の学生にライバル心が燃え上がり、日本でもワインを造っていると彼らに認めてもらえるようになりたいと思いましたね。お酒に関わる仕事がしたいともともと思っていたのですが、この時に『世界に通用するお酒を造ろう』と決心したのです」。
帰国後にワイン造りを第一希望として就職活動を進めた田村さん。メルシャンに入社してから現在に至るまで、一貫してワインに携わってきたプロフェッショナルだ。

『メルシャンならではのコンサルティング』
続いては、コンサルティングをする際に重視していることや、サポートの具体的な内容を紹介していこう。あわせて、メルシャンがコンサルティングにかける思いについても深掘りしていきたい。
▶︎日本ワイン業界に貢献したい
「ワインは素晴らしい自然の恵み」だと話す藤野さん。「ワインというのは本当にデリケートで優しいお酒です。微生物や酸化に対して弱いため、醸造する上で気を付けなくてはならないことが沢山あります。瓶詰めが終わるまで、人間がきちんと守ってあげなくてはなりません。そして、『守る』という作業は、とても難しいことなのです」。
スタートアップワイナリーの中には、ワインへの憧れを持ってワイン造りを始めた人も多い。しかし、憧れだけでは正しいワイン造りはできない。自分が憧れるワインと同じレベルの品質を実現することは、想像以上にハードルの高い取り組みなのである。そのハードルを乗り越えるには、醸造における基本の徹底が必要不可欠だ。
丁寧に、熱い志を持ってサポートをおこなう藤野さん。コンサルティング事業を始めたばかりの頃には、初歩的なことを知らないままにぶどう栽培とワイン造りをしようとしているワイナリーがいることに驚いたが、同時に強い使命感も抱いた。「自分自身がメルシャンで培ってきた技術と経験を伝えることで、日本ワイン業界に貢献できるはずだ」と考えるようになったのだ。

▶︎基本を重視することの大切さを伝える
ワイン醸造の支援をおこなう上で、藤野さんはさまざまなセオリーを伝えている。まずは、ぶどうの品質において基本となる考え方である「適熟」だ。また、ぶどうを適切な熟度に持って行く上で欠かせないのが「防除」である。藤野さんは「防除なくして適熟に到達することは出来ません」と話す。
品質と生産量を上げるためには、防除を適切に行うことが鍵になる。メルシャンのコンサルティングを受けると、栽培管理に強いOBや社員から直接指導を受けることができ、正しい方法を学ぶことができるのが大きなメリットだ。
「赤ワイン用品種の場合には、きちんと着色することや糖度が十分に上がることも求められます。しかしその『基本』が非常に難しいため、栽培担当者との密な連携を持つことを意識してサポートしています」。
防除の重要性については、田村さんも口を揃える。だが、スタートアップワイナリーの中には薬剤を使いたがらない人も多いという。「お金がかかるから」「有機栽培がしたいから」などの理由からだというが、結局病気を発生させてしまい薬剤を使うことになるケースが見られる。病気になってから薬剤を使うのでは、ぶどうにとってもワインにとってもプラスにならない。
田村さん達は、農林水産省が実践を呼びかけている指針である「IPM(総合的病害虫・雑草管理)」の考え方に基づいて、適切な圃場管理をおこなうことの重要性を指摘する。
「シャトー・メルシャンでは、薬剤をむやみに使うことはしません。適切な草刈りを中心とした環境整備を実践しつつ、予防の観点で防除をおこなっているのです。サポートするワイナリーにも、病気の兆候が出てから薬剤を使用したのでは遅いことをしっかり伝えています」。
ぶどうの品質を向上させるために欠かせない作業として、その他にしっかりと指導しているのが、「選果」「貯酒管理」などだ。正しい対応が必要な理由から、実際におこなう方法までを丁寧に学ぶことができるのは、メルシャンが提供するコンサルティングならではだろう。認識のギャップを埋めて正しい技術で実践することが、より品質が高いワイン造りに直結するのだ。

『コンサルティング事業のこれから』
最後に、メルシャンがコンサルティング事業を推進していく上で掲げる、今後の目標について伺った。
栽培や醸造だけでなく、ワイナリーのあらゆる悩みを解決し「繋ぐ」存在になることを目指すメルシャン。コンサルティング事業の展望について、田村さんは次のように話す。
「今後は、ワイナリーを設立する前段階のサポートもできるようにしていきたいですね。例えば『圃場選び』や『品種選び』といった段階からサポートできるよう、包括的なサービスを展開していこうと思っています」。
▶︎日本ワインをさらに盛り上げる施策
具体的な施策についても、ふたつ挙げていただいた。ひとつは、コンサルティング事業を通じて、地域への貢献に取り組むことだ。キリングループが大切にしている「CSV(クリエイティング・シェアード・バリュー、共有価値の創造)」という考え方に基づき、ローカルサプライチェーンを繋げ、地域一丸となって日本ワインを盛り上げていく。
「シャトー・メルシャンの利益を考えると、どうしても周囲と利益の取り合いになってしまうという課題がありました。しかし、コンサルティング事業という形であれば、地域を繋ぐ役割に徹することができます。いろいろな場所でそれぞれに熱い思いを抱いて頑張っている人たちを『繋ぐ』役割を、私たちが担いたいのです」。
もうひとつは、販路開拓のサポート体制を作り上げることだ。栽培や醸造だけでなく、「販路」にも悩みを抱えているワイナリーは数多い。
メルシャンはグループ会社として、自社以外のワインも取り扱う販売会社「ワインキュレーション株式会社」を有している。ゆくゆくは、コンサルティング先のワインをこの販路に乗せることを考えているそうだ。
「関わってきたワイナリーのワインを、メルシャンのワインと一緒に販売するチャンスを提供出来ればと考えて検討を進めています」。

▶︎コンサルティングサービス 利用者の声
2025年5月30〜31日、メルシャンは東京都渋谷区にて「シャトー・メルシャン フェスティバル 2025 ~日本を世界の銘醸地に~」を開催。日本ワインのおいしさや楽しさを伝え、日本ワインの更なる認知拡大を目的としたイベントは、たくさんの来場者でにぎわった。
フェスティバル当日は、シャトー・メルシャンの3ワイナリーが参画した他、メルシャンがコンサルティング事業を提供している岩手県花巻市のワイナリー「アールペイザンワイナリー」と「MKファームこぶし」がセミナーに登壇。メルシャンと共に造り上げたワインの販売も実施して好評を博した。メルシャンのコンサルティング事業を利用したワイナリー関係者の率直な感想を聞くことができたので紹介したい。
「メルシャンの栽培醸造コンサルティングを受けて、自分たちの立ち位置を知ることができました。現在の醸造技術がどのくらいの位置にあり、自分たちのぶどうでどこを目指すのかを示していただけたことが大きな収穫でした。ぶどう栽培とワイン醸造は長いスパンでの取り組みが必要です。スタートアップワイナリーとして、メルシャンの知見を活用しながら、岩手で銘醸地を目指していきたいと思います。渋谷でのフェスティバルに参加して、お客様の反応を直接感じられたことも非常によかったです」。
(「アールペイザンワイナリー」髙橋さん)
「ワインやぶどうに対する的確なアドバイスをいただけたことがよかったです。正しい方向性を示してもらえるのは非常にありがたいことです。栽培に苦労している方々に対してテクノロジーを活用した効率的な栽培システムを、メルシャンと一緒に広めていきたいです。渋谷でのフェスティバルでは、メルシャンのアドバイスを受けて造ったワインを紹介できて、東京の方々が新しいものに興味を持ってくれたことも嬉しかったですね」。
(「MKファームこぶし」堰根さん)

『まとめ』
悩みを抱えるすべてのワイナリーに向けて、ある言葉を伝えたいと田村さんは言う。
「『失敗を共有しなさい』という浅井さんの言葉があります。ワイン新興国の日本が世界で頑張るには、失敗を共有してみんなで成長することが大切です。あらゆる経験をシェアして繋がり、日本ワイン全体としてよくなっていけるように尽力していきましょう」。
田村さんたちの熱意が伝わり、知り合いのワイナリーから、「応援しています」「よい取り組みだから、ぜひ頑張ってほしい」と声をかけてもらえることも増えてきたのだとか。また、「実は、私たちも困っている」と打ち明けてくれる方や、「あのワイナリーが困っているみたい」との情報を貰えることもあるという。
「ワイン造りの技術を向上させるためには、よいワインを造ったという経験を通してワイン醸造の一連の工程をマスターしていくことが欠かせません。失敗は成功の元ですので、まずは正しい方法で経験を積むことが大切です。ワイン造りに関する悩みがあれば、どんなことでも気軽にご相談ください」。
悩みや相談したいことがあるワイナリー関係者は、ぜひ気軽に、問い合わせ専用アドレスに連絡してみていただきたい。
「造り手の皆さんには、自分が本当に美味しいと思うワインを造って提供する喜びを感じてほしいですね。『自信を持って世の中に送り出せるワインを造る』ということを、それぞれのワイナリーでまっすぐに目指してください」と、藤野さん。
「今後は、コンサルティング事業を通じて関わらせて頂いたワイナリーのワインを紹介できる場を増やしていきたいですね。シャトー・メルシャンが開催するイベントでも、一緒にワインを造る仲間としてコラボレーションしていきます。また、飲み手の皆さまも、ワインだけではなく造り手にも興味を持って、日本ワインをもっと楽しんでください」と、田村さん。
メルシャンが提供するワイナリー向けのコンサルティング事業は、ワイナリーの支援だけではなく、日本ワイン産業の持続的な成長に向けたパイプラインとなることを目指す。日本ワイン業界において、さらに必要とされる存在になっていくことだろう。

基本情報
| 名称 | メルシャン株式会社 経営企画部 |
| お問い合わせ先 メールアドレス | コンサルティング代表: 04034_Ni@mercian.co.jp |
| シャトー・メルシャン HP | https://www.chateaumercian.com/ |