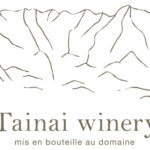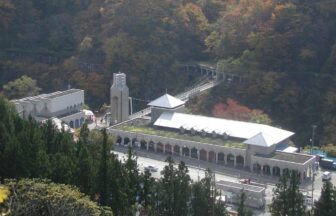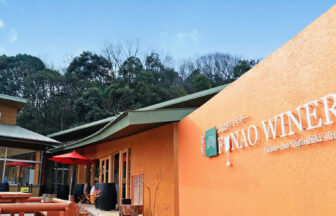岩手県陸前高田市にある「ドメーヌ ミカヅキ」は、2021年に創業したワイナリーだ。代表を務める及川恭平さんは陸前高田市出身。2011年に東日本大震災が発生した当時、まだ高校生だった及川さんは、故郷が受けた甚大な被害を目の当たりにして、復興のために何ができるかを考え抜いた。そして、地域の復興のためにワイナリー事業をスタートさせることを決意したのだ。
ドメーヌ ミカヅキでは、ぶどうとりんごを自社畑で栽培している。及川さんが思い描く通りにワイナリーをブランディングしていくため、手がけるぶどう品種は厳選した1品種のみ。陸前高田の豊富な海産物に合わせられるアルバリーニョだ。
2021〜2023年まではシードルの醸造のみを実施。酸が高くドライなテイストのシードルは、たくさんの人に陸前高田市の復興を印象付ける存在となった。
そして、2024年には満を持して、自社畑のアルバリーニョが初収穫を迎えた。ドメーヌ・スタイルのワイン造りを目指すドメーヌ ミカヅキは、ワイン造りに取り組むのは自社畑のぶどうが育ってからと決めていたのだ。今後は、アルバリーニョの特性を生かし、バリエーション豊かな「海のワイン」を造っていく計画を立てている。
今回は、2023年以降のぶどう栽培とワイン醸造についてを中心に、新たに始めた取り組みと、今後の展望についても詳しくお話いただいた。ドメーヌ ミカヅキの最新情報を、余すところなく紹介していこう。
『ドメーヌ ミカヅキ 2023〜2024年のぶどう栽培』
まず最初に、ドメーヌ ミカヅキの2023〜2024年のぶどう栽培を振り返ってみたい。天候に大きく左右されるぶどう栽培では、年ごとの気温や降水量、日照時間などがワインの味わいに直結する。
ドメーヌ ミカヅキがある陸前高田市では、2023〜2024年がどのような天候だったのかに注目しながら、栽培管理においての取り組みと、新たな挑戦についても触れていこう。
▶︎2023年の天候とぶどう栽培
2023年は、及川さんが果樹栽培をしてきた中で、これまで経験したことのない猛暑の年だった。
「りんごは涼しい気候を好む果樹なので、非常に困りましたね。うちだけではなく、近隣のベテラン農家さんたちも生産量が大幅に減少してしまったようでした。暑さ対策としては、葉で影を作るように努力しました。しかし、無事に育つようにと祈るしかなかったのが、正直なところです」。
一方、ぶどう畑では、暑さに負けることなくアルバリーニョが健全に育った。雨が少なかったために、やや収量減と減酸の影響はあったものの、むしろよく熟して品質は申し分なく、陸前高田市でおこなうぶどう栽培に適した品種としてアルバリーニョを選んだことが正しかったと実感できた年だったという。
「アルバリーニョが持つ陸前高田での適正を実感しました。陸前高田市は岩手の中では暖かいのですが、それでもアルバリーニョにとってはもう少し積算温度が欲しいくらいだったため、むしろ気候変動が追い風となっているのを年々感じています。収穫したぶどうのデータを測定してみると、酸、バランス、品が整い、ポテンシャルのある出来だということがわかりました」。
ワイナリー経営をする上で、栽培する品種を選択する際にはさまざまなケースを想定しておく必要がある。例えば、複数の品種を栽培すれば、出来や収量が思わしくない品種があっても、他の品種でカバーすることが可能だろう。しかしその分、必要なノウハウや設備も余分にかかってくる。一方、栽培する品種が少ない場合はアピールポイントが絞りやすいのでマーケティングが容易になるというメリットはあるが、気候や病害虫の影響で被害が出た際に収量が減少するリスクは避けられない。
「どんな道を選んでもメリットとデメリットがそれぞれあるのですが、ドメーヌミカヅキではアルバリーニョのみに絞ったメリットの方がより大きいと感じています」。

▶︎2024年の天候とぶどう栽培
続く2024年は、2023年とは対照的な天候だった。陸前高田市は台風や雨の被害に悩まされたのだ。そのため、りんごにとってはそれほど問題なかったが、ぶどう栽培にとっては厳しい年となった。ドメーヌ ミカヅキの自社畑のぶどうが初収穫を迎えた年でもある2024年。及川さんはどのように乗り切ったのだろうか。
「珍しいことなのですが、台風が太平洋側から陸前高田市を直撃する事態となりました。三陸の太平洋沿いでは、多くの場合、台風は南からやってきます。また、ほとんどの場合、この辺りに到達する頃には温帯低気圧に変わって消滅するのです」。
台風や、それに伴う雨の影響は決して小さくはなかったが、なんとか無事に初収穫できたのは、及川さんが普段から努力を欠かさなかったからこそ。こまめに畑に通って草刈りや病果の除去などを怠らなかったことが幸いした。
雨が多く土中の水分量が増えたことで、本来はバラ房のアルバリーニョも粒が肥大してしまったが、もともと果皮が厚い品種なので裂果することはなかった。雨に対しても強い品種だと改めて実感したそうだ。
2024年はひとりで収穫作業をおこなったという及川さん。毎日の天候に振り回された年だったが、無事に収穫を迎えて、込み上げるものがあったという。

▶︎「ビオディナミ農法」を導入
ドメーヌ ミカヅキでは、ブランディングの一環として、「ビオディナミ農法」を導入している。ビオディナミ農法とは、ドイツの思想家ルドルフ・シュタイナーが提唱した理論に基づく農法だ。自然の力を引き出すことを重視した有機栽培の一種で、天体の動きや月齢に基づいて農作業をおこなうという特徴を持つ。
月の満ち欠けや潮の満ち引きのリズムを重視するビオディナミ農法はスピリチュアルな色合いも濃いからこそ、導入するには科学的な背景をしっかりと整備する必要があったと及川さんは話す。
「単一品種のみの栽培でアルバリーニョを採用したのは、当初からビオディナミを取り入れようという狙いを持っていたからです。だから”ミカヅキ”でもあるんです。対病性が強いのはもちろん、ビオディナミに則った、酸化防止剤である亜硫酸塩にあまり頼らないワインを作ろうとすると、pH(水素イオン指数)が低い品種を選ぶ必要があるので、アルバリーニョが最適だと考えました」。
「しかも、陸前高田は氷上花崗岩という特殊な土壌です。ぶどう畑からは水晶が取れ、近隣からは牛の角も手に入るため、『プレパラシオン(調剤)』が自前で調達できます。それらのいわゆる『ナラティブ』は、日本遺産である陸前高田の金山の歴史的価値を高めることにも繋がります」。
畑も市内で点在し、それぞれ環境が異なるので単一品種でも違いを出せる。海も近いので有機的で安価な資材が手に入りやすく、風も強いので畑の換気がよい。また、及川さんがフランスで働いていたワイナリーもビオディナミを実践している生産者だったため、すでに経験もあった。無理にやるというよりも、実践できる要素が絶妙に噛み合っていたのだ。

ビオディナミ農法を取り入れて気づいたことは、雨が非常に多かった2024年でも、なんとか無事収穫にこぎつけたことだ。当初から狙いとしてはあったが、実際観測するまでは水面下で動いていた。昨年は家庭の事情も重なり思うように畑に行けない中ではあったが、ぶどうが元気に育っていた様子を見て可能性を実感したそうだ。
及川さんがビオディナミ農法を採用したのは、ワインに付加価値を与え、より効果的にアピールしていくためだ。「日本にもこういうワインを造っているワイナリーがあるのか」と思ってもらうと共に、「デメター」という国際的な第三者認定を得ようと考えて地道に整えている。
「今後も観測を重ねていきたいと思います。日本でのデメター認証取得の難易度はとても高く、ドメーヌでないと極めて困難です。土地の選定や長期計画、資本や販売文脈も絶妙なコントロールが必要ですね。品種はあくまでも手段なのです。」
近年、ウクライナ問題などの影響で肥料価格が高騰。化学肥料を使う慣行農業は環境への影響があるだけでなく、農家の負担が大きくなりすぎて持続が難しい状況に陥っている。一方で、地域で資材を循環させられるビオディナミ農法は、より持続可能な農法に近いと言えそうだ。
「畑には他事業者の養蜂場が隣接しています。ワインのプロダクト自体は確かに科学ありきなのですが、余白の部分も多く存在していると考えています。教科書だけでは見落としてしまう土地勘や市場性、インフラや政治や歴史などの部分も鑑みて反映させる必要があると思っています」。
及川さんが数年間かけて観察を重ねたビオディナミ農法の可能性には、多くの人が耳を傾けたくなることだろう。ブランディングの一環としてどのような効果が出るか、今後に期待したい。

『ドメーヌ ミカヅキのワイン造り』
続いては、ドメーヌ ミカヅキのファーストヴィンテージワインに話題を移そう。
2024年は、自社栽培のぶどうを使用して、知り合いのワイナリーで醸造。多くの人から期待される中、非常に大きなプレッシャーを感じたと話してくれた及川さん。当面の目標は、安定した品質のワインを造ることだ。
▶︎ドメーヌ ミカヅキのファースト・ヴィンテージ
「醸造工程でのリスク軽減ができるように、温度管理にはしっかりと気を配りました。もちろんクリーンに。初年度は果皮を漬け込むオレンジワインの手法で仕込みましたが、今後はアルバリーニョの特徴を生かして、バリエーション豊かなワインを造っていこうと思っています」。
及川さんが経験した初めてのワイン造りは、いろいろな苦労を乗り越えてワインができたという喜びでいっぱいだったそうだ。
「ドメーヌ ミカヅキのワインを、たくさんの方に飲んでもらいたいですね。陸前高田でワインを造ることで地域に交流を産み出し、まちづくりのためのひとつの骨子になると感じています」。
ワインのエチケットは、丸くくり抜かれたデザインが特徴だ。ワイナリー名の由来でもある「月」と、「青海波(せいがいは)」という海をイメージさせ平和を象徴する伝統的な和紋をモチーフにしている。ネーミングは「満ちていく」。三日月が満月に向かうようにという「発展」の願いと、気分が満ちていくことへの意味を込めた。
実は、ドメーヌ ミカヅキというワイナリー名には、10個近くもの由来が隠されているのだという。今後少しずつ全容を明らかにしていくということなので、秘密が明かされていくのを楽しみに待ちたい。

▶︎三陸産の海の幸と共に味わうワイン
2024年ヴィンテージのオレンジワインは、ぜひ三陸産の海産物と合わせて欲しいと話してくれた及川さん。
「陸前高田の牡蠣はミネラル分と塩味が多くボリューミーで、すっきりした味の白ワインだと物足りないはずです。そのため、ファーストヴィンテージは、あえてオレンジワインにしました。ナチュラル寄りの滋味深いワインとよくマッチすると思いますよ」。
陸前高田市では、牡蠣以外にもタコやムール貝など豊富な海産物が楽しめる。現地を訪れて海の幸とワインを楽しむ旅は、想像するだけで心が踊る。
また、ドメーヌ ミカヅキではすでに、ワイン・ツーリズムを独自に開催しているそうだ。ソムリエ資格も持つ及川さんがオーガナイズするツーリズムは、さながら「食のアトラクション」。船に乗って牡蠣棚を見学した後には、牡蠣や寿司と一緒にワインを楽しみ、夜は満点の星空を眺めながらワインを心ゆくまで楽しむという趣向だ。
ドメーヌ ミカヅキは、2025年夏からワイナリーとして使用する建物の改装工事に入り、2026年にはワイナリーをオープンする予定。ワイナリーができればいよいよ、ワイン・ツーリズムの取り組みも本格始動する。最新情報は公式サイトやInstagramなどで発信するということなので、気になる方はこまめにチェックしていただきたい。

▶︎りんご栽培とシードル醸造も、新たなステージへ
ワイナリー立ち上げ以来、シードル醸造をおこなってきたドメーヌ ミカヅキだが、2025年現在もりんごの樹の植え替えを進めている。
「陸前高田市は古くからの果樹産地です。特にりんごは、他のエリアでは栽培されなくなったような、歴史がありレアな品種が今でも残っています。温暖化や高齢化や高台移転によって、近年急速にりんご畑は減少していますが、まちの宝だと思うので、自発的にそうした品種を保存しています。昔の品種は酸味と香りが強いものが多く、温暖化にも対応できます。加工品種としては最適で、一石二鳥ですね。」
また、この地域に溶け込んで農地を拡大するには、りんご栽培を手がけていることは強い武器になる。ただし、りんごは一般的には防除が必要な果物なので、ぶどうとりんご、それぞれに最適な方法での管理をしながら続けていきたいそうだ。

『まとめ』
今後は、ビオディナミ農法に関する国際認証の取得も視野に入れているドメーヌ ミカヅキ。海外展開も視野に入れており、認証の取得は国外で流通させるための準備の一環でもある。
及川さんが取得を考えているのは、世界で最も基準が厳しいといわれるオーガニック認証のひとつである。ビオディナミ農法で生産された農作物や加工された製品にのみ認証マークをつけることが認められ、認可されることは一種のステイタスでもあるという。
「日本ではまだ取得しているワイナリーはないので、挑戦してみようと思っています。世界や業界への認知に繋がるでしょう。また、ドメーヌ ミカヅキが震災のイメージを払拭して、さらに上回るためには、新たなステージが必要だと思っています」。
まだ生産量は少ないが、より多くのぶどうを栽培するため、さまざまな人の力を借りて徐々に畑を拡大中だ。
「畑を見たい、ツーリズムに参加したいなどのご要望があれば、ぜひ直接声を寄せていただけたら嬉しいです。できる限り応えていきたいですし、いろいろな方と直接対話する機会をたくさん持って、より親しまれるワイナリーになっていきたいですね」。
ドメーヌ ミカヅキの今後の躍進に、これからも注目していきたい。

基本情報
| 名称 | ドメーヌ ミカヅキ |
| 所在地 | 岩手県陸前高田市 |
| HP | https://domaine-mikazuki.com/ |