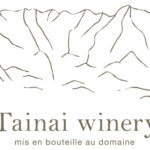埼玉県北西部、秩父盆地の西部にある秩父郡小鹿野町(おがのまち)は、日本百名山のひとつである両神山(りょうかみさん)をはじめとした、奥秩父山地の豊かな自然に抱かれた土地だ。
そんな小鹿野町にあるのが、今回紹介する「秩父ワイン」。ある好奇心旺盛な農家が奥秩父でワイン造りを始めたのは、実に80年近くも前のこと。移りゆく時代ともにさまざまな出来事を乗り越えて、秩父ワインは伝統の味を守り抜いてきた。
秩父ワインの創業者である浅見源作氏は、日本ではまだワインというお酒が一般的ではなかった時代に、なぜワイン造りに挑戦したのだろうか。
秩父ワインの取締役を務める村田道子さんに、浅見氏がぶどう造りを始めた経緯と、ワイン醸造に成功するまでにたどった険しい道のりについてお話いただいた。
また、その後の秩父ワインがどんな点にこだわってぶどう栽培とワイン醸造をおこなっているのか、今後の展望などについても詳しく伺うことができたので、詳しく紹介していこう。
『秩父ワインができるまで』
秩父ワインの創業者である浅見源作氏は、秩父小鹿野町生まれ。養蚕や農業などを生業とし、新しいことへの挑戦を恐れない人物だった。
浅見氏がぶどう栽培とワイン醸造に取り組んだきっかけは、小説「ロビンソン・クルーソー」を読んだこと。自分たちの手でさまざまなものを作り出す暮らしに憧れたのだという。秩父ワインが誕生するまでの物語を振り返ってみよう。
▶︎ワイン造りを志す
2025年現在、秩父ワインの代表を務めるのは5代目となる島田昇さんで、村田さんの兄である。兄妹の曽祖父にあたる浅見氏がワイン造りを志した当時は、今のように手軽に情報を得られる時代ではなかった。もちろん、奥秩父でワインを造っている人など他にいるはずもない。
そこで浅見氏は、新潟県上越市の「岩の原葡萄園」の創業者で、「日本のワインぶどうの父」と呼ばれた川上善兵衛氏の著書「実験葡萄全書」でワイン造りを学ぶことにした。東京・神田の古書店に依頼した浅見氏は、中古本が出たという知らせを受けた際、なんと秩父の山奥から東京まで自転車で向かったという。
「本の代金だけを握りしめて、自転車で2泊3日の野宿旅に出たそうです。しかも、途中の食事代は、編んで持参した草履(ぞうり)を物々交換してまかなったと聞いています」。
浅見氏の熱意を伺い知ることができる、興味深いエピソードである。
購入した書籍には英語表記もあったため、読解にはずいぶん苦労したことだろう。また、醸造機器は図解があるのみで詳細な解説がなかったため、近所の大工さんに図解を見せて、見よう見まねで圧搾機を作ってもらったそうだ。
さらに、当時の秩父ではぶどうの苗の入手も難しかった。そのため、峠を越えて長野まで出かけて苗を背負って秩父に戻り、苦労して運んだ苗を大切に植え付けた。
1930年代には数々の困難を乗り越えてぶどう栽培に成功し、ワイン造りの準備を進めた浅見氏。1940年には醸造免許を取得して、ようやくワイン造りをスタートすることになった。

▶︎「源作印」ワインがたどった道のり
だが、「秩父葡萄酒」として売り出したワインの販売は決して順調ではなかった。当時はまだ、ワインという見たことも聞いたこともないという人も多い時代。お酒がなかなか売れなかったのも無理はなかった。
その後、第二次世界大戦中になると、潜水艦や魚雷探知の水中音響機器(ソナー)に使用する目的でワインは軍需物質としての増産が推奨された。だが、戦後の貧しい時代には嗜好品であるワインは売れず、また苦しい時代が続いた。
転機が訪れたのは、1959年のことである。宗教儀式に使うワインを求めて、埼玉県浦和市のフランス人神父の兄弟が、秩父ワインを訪ねてきたのだ。
「日本で造られるワインは甘口が多かった中、うちのワインは当時から酸っぱくて渋い赤ワインだったので、神父さんから『まるでボルドーワインのようだ』と評価されたのです」。
秩父ワインが本場の味を再現しているという評判は、口コミでキリスト教会周辺から在日フランス人コミュニティ、そして日本の文化人へと伝わっていった。また、作家の五木寛之氏が雑誌で秩父ワインを取り上げたことも、知名度をさらに上げるきっかけとなったそうだ。
奥秩父の一農家が独学で造ったワインはマス・メディアにも度々取り上げられ、徐々に人々の知るところとなっていったのだ。浅見氏がワイン造りを開始して、実に30年が経ったころのことだった。
94歳まで生きた浅見氏を、ひ孫である村田さんは「元気でユニークなおじいさんだった」と振り返る。
「プロレス好きで、剣道や書道、絵画もたしなむ多趣味な人でした。知識欲旺盛で自分のルーティンを大切にしていて、昼寝は欠かしませんでしたね。『昼寝をすると、1日が2日になるから』と言って笑っていたのを、今でも鮮明に思い出します」。
並々ならぬ情熱をかけて続けてきた浅見氏。ワイン造りに対する深い思いを残したいと考えた家族たちは、「源作印」という創業者の名前をワインに冠したのだ。

『秩父ワインのぶどう栽培』
ここからは、秩父ワインのぶどう栽培について見ていこう。自社畑の土壌や気候条件、栽培している品種などについて詳しくお話いただいた。
栽培管理における独自のこだわりと特に注意している点、ぶどう栽培における課題など、秩父ワインならではのぶどう栽培を深掘りしていきたい。
▶︎自社畑で栽培している品種
秩父ワインの自社畑で栽培しているぶどうは、いずれも2000年前後に植え替えた欧州系品種だ。浅見氏が植栽したぶどうの中で残っているのは、日本の気候に合っていて病気に強く育てやすいヤマブドウのみである。栽培している品種を以下に挙げる。
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- ソーヴィニヨン・ブラン
- シャルドネ
- メルロー
- ヤマブドウ
欧州系品種は湿気に弱いため、植え替えのタイミングで大々的に圃場の整備をおこなった。現在は簡単に設置できる雨よけも商品化されてきているが、2000年頃のレインカットは大掛かりな土木工事が必要だったのだ。
レインカットの枠組みを土中に埋め込む際に、せっかくなら土壌改良もしようと決意。唐沢地区にある畑の表土から1mほどを掘り返し、礫(れき)状の石灰を入れてから土を戻した。
続いて、「燕麦(えんばく)」を育てて過剰な栄養分を取り除き、ぶどう栽培に適した環境を作り上げてから、新たな品種を植栽した。秩父ワインのフラッグシップ・シリーズ「KARASAWA」は、丁寧に土壌環境を整えた自社畑から生まれているのだ。

▶︎自社畑の特徴と周辺の気候
樹齢20年を超えた欧州系品種の中で、自社畑の土地への適性が高いのはメルローとシャルドネだ。
「フランスなどの銘醸地のワインを飲んだ時に、続けてうちのワインを飲むと、『うちのワインも負けていないな』と思うのです。本当に美味しいですよ」。
ソムリエ資格を有する村田さんも自信を持っておすすめできるというワインの美味しさの秘密のひとつとして、秩父ワインの自社畑が持つ、ある特徴について教えてくれた。
秩父ワインがある秩父郡小鹿野町は、周辺と比較して雨量が少ない土地というわけではない。だが実際には、ちょっとしたエリアの違いで雨の振り方が違うことがあるという。盆地であることや、山や川などの地形条件が影響していると考えられる。
「川を挟んで対岸は雨が降っているのに、反対側は全く降っていないということもよくあります。畑周辺の実際の降雨量は、気象台が発表している小鹿野町の数値よりも少ない感じがしますね」。
土壌改良をしたタイミングで、水はけ改善のための施策もおこなったので、台風が直撃しない限り雨による大きな問題はない。自社畑は日当たりもよく、発電事業者から土地を譲ってくれないかとの打診を受けることも度々あるほどだ。
特に、標高200〜300mにある唐沢の畑は先祖代々受け継いできた土地で、昔から何を作ってもうまくいくとされてきた畑だ。かつては地域の畑それぞれに等級がつけられており、唐沢は一級畑に区分されていたという。
「一級畑というとフランス・ボルドーのような感じがするので、ワイン造りの仲間にその話をするとうらやましがられます。傾斜はそれほど強くありませんが、畑の脇には小さな沢が流れていて、土中の余計な水分は沢の方へと逃げていきます。また、夜になると近くの山や川から冷気が流れ込んで気温がぐっと下がるので、ぶどう栽培向きの条件が揃った土地なのです」。

▶︎ぶどう栽培におけるこだわり
秩父ワインを訪れる見学者は、畑の手入れの丁寧さに驚くそうだ。畑の広さは合計2haほどで、栽培管理のほとんどは手作業でおこなっている。草刈りは風通しを邪魔しない程度に実施し、景観にも気を配る。
栽培工程で特に力を入れているのは、枝葉の管理だ。以前はゴールデンウィーク頃だった芽吹きが、最近はさらに早まってきたため、ぐんぐん伸びた枝の剪定を丁寧に実施する。樹齢20年を超える樹も多いため、秩父の厳しい冬に耐えられる状態にすることが必要だ。
秩父の冬は寒く、気温が氷点下を下回ることも多いが、降雪量は少ない。ぶどうの樹がすっぽりと覆われるほど雪が積もれば問題なく越冬できるが、雪が少ない地域では凍害の恐れが出てくる。特に老木は、厳しい環境に耐えられず枯れてしまうこともあるだろう。
そのため、秩父ワインの自社畑では、毎年少しずつ樹の植え替えも進めている。一度に植え替えると一時的に収穫量が激減してしまうため、収量に影響が出ないよう段階的に対応しているのだ。
「凝縮感のあるぶどうを収穫するため、収量制限も徹底しています。ぶどうの樹にきちんと向き合い、ぶどう自身がどんな手入れを必要としているのかを確認しながら作業を進めています」。

▶︎奥秩父でぶどう栽培をする苦労
山深い秩父には多くの野生動物が生息していており、収量を確保するためには獣害対策が欠かせない。新しい畑を造成する際には、畑の周囲にステンレスのネット柵を張り巡らせる工事も実施した。だが、柵があっても地面を掘って柵の下から侵入してくる動物もいるため、場合によっては柵を地中に埋め込む作業が必要になることもある。
よく姿をあらわすのは、ハクビシンやノウサギなど。かわいい動物ではあるが、ぶどうを食べてしまう動物は畑から遠ざけなくてはならない。また、柵では防ぎきれない鳥には、防鳥ネットを使用している。
「畑全体に防鳥ネットを張り巡らせるのは本当に大変な作業なのですが、せっかく育てた大切なぶどうを食べられるわけにはいかないという一心で、大きな脚立を使って4人がかりで作業しています」。
防鳥ネットを潜り抜けてぶどうを食べてしまう鳥もいるため、完全に町外を防ぎ切ることは難しい。自然相手におこなう農業の厳しさを改めて思い知らされる。

『秩父ワインのワイン醸造』
続いて紹介するのは、秩父ワインのワイン醸造について。醸造には、自社畑のぶどうの他、山梨などから買い付けたぶどうも使用している。
秩父ワインはいずれも「源作印」というブランド名でリリースしており、トップキュベは自社畑で栽培したぶどうだけを使った銘柄だ。さまざまな価格帯のワインが揃うラインナップは、いつもの食卓で気軽に楽しめるものから、特別なハレの日に飲みたいものまで幅広い。
多くの銘柄があるとはいえ、「料理を引きたててくれるワインであること」は、秩父ワインの全ての銘柄に共通している。ワインがあるから料理がより一層美味しいと感じられる存在を目指して、食中酒として造られているのが秩父ワインの特徴なのだ。
秩父ワインの製品は多くのホテルやレストランで重用されており、ペアリングディナーのイベントなども頻繁に開催されている。
「イベントに参加していただいたお客様から、ペアリングに関するご質問をいただくと、話が盛り上がってしまうこともよくあります。いろいろなワインとペアリングのご提案を直接ご紹介できるイベントは、とても楽しい時間ですね」。
▶︎「源作印 甲州 樽貯蔵」
28種類もある秩父ワインの製品ラインナップの中から、村田さんおすすめのワインをいくつか紹介しよう。それぞれのワインに合わせたい料理も挙げていただいたので、あわせて見ていきたい。
まずは、「源作印 甲州 樽貯蔵」。山梨産の甲州をフレンチオーク樽で熟成したワインで、村田さんイチ押しのヴィンテージは2009年だ。
「飲んだ後に広がる香りが非常に華やかで、余韻が長いワインです。クリームやバターを使った魚のソテーと合わせていただくと、お料理もワインもそれぞれのよさがより引き立つと思います。タルタルソースやアジフライも合いますので、ぜひいつもの食事と共に味わってみてください」。
美味しくて、あっという間に1本全て飲みきってしまうので困っていると笑う村井さんが「源作印 甲州 樽貯蔵」に付けた別名は、ずばり「幸せになれるワイン」。疲れたり嫌なことがあった時にこそ「源作印 甲州 樽貯蔵」を開けて、華やかな味と香りに癒されたい。

▶︎「秩父 KARASAWA メルロ」
続いて紹介するのは、「秩父 KARASAWA メルロ」。上皇陛下がかつて埼玉に行幸された際に召し上がったこともある1本だ。海外のメルローのようにガツンとした果実味はないものの、非常にエレガントで上品な飲み口である。
「タンニンが滑らかで、ひと口飲み終わると、また次のひと口が飲みたくなるようなワインです。お祝いの席などで開けていただけるとよいと思います。私自身が、お正月のお節料理と一緒に飲むワインとして選ぶのが『秩父 KARASAWA メルロ』です。ローストビーフなどの肉料理はもちろん、濃いめに味付けた筑前煮にも合いますよ」。
特別な日のごちそうと一緒に楽しむエレガントなメルローは、うっとりするような美味しさだろう。
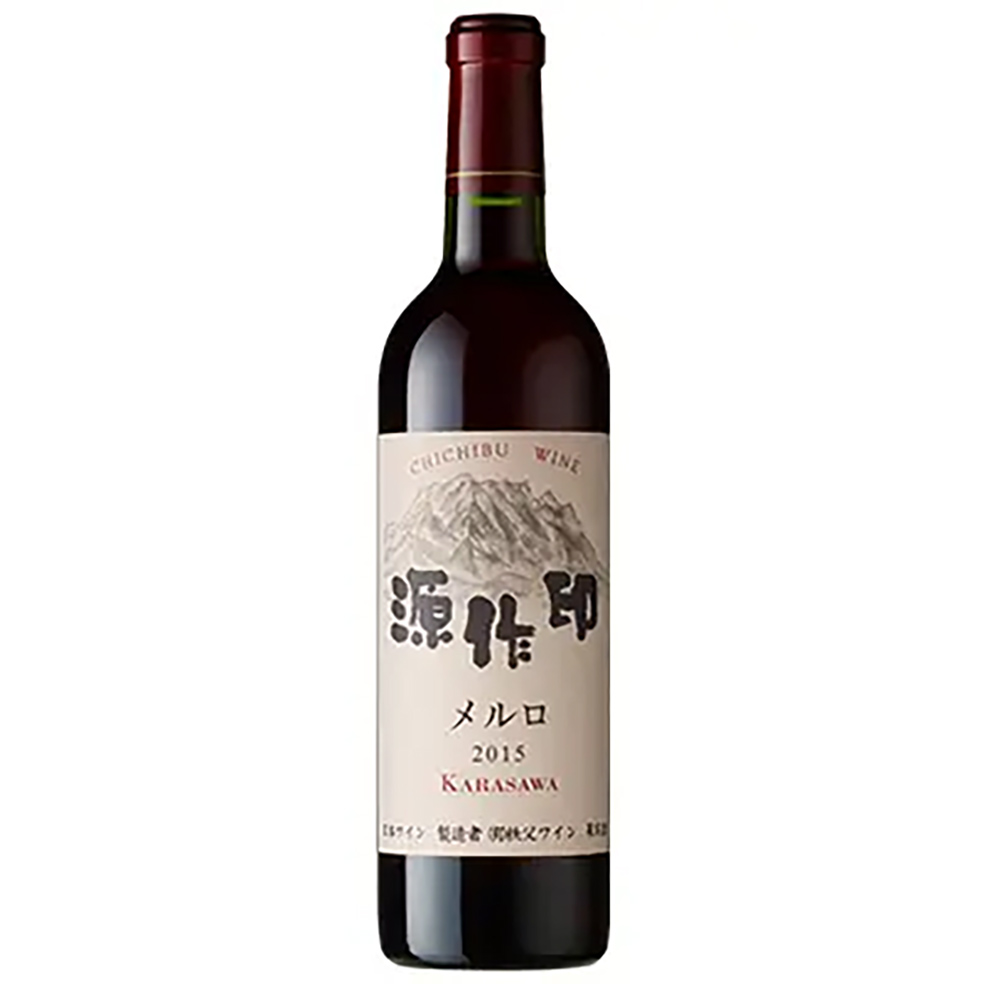
▶︎「秩父 KARASAWA メルロ リムーザンオーク樽貯蔵」
「秩父 KARASAWA メルロ リムーザンオーク樽貯蔵」は、秩父ワインの醸造におけるこだわりが感じられる銘柄だ。秩父ワインでは、ぶどうの品種ごとにさまざまな種類の樽を使い分けている。
「メルローにはリムーザンオークが一番合うというのが、社長のこだわりです。ヴィンテージによってはいくつかの種類を使い分けてメルローを樽熟成させることもありますが、収量が少ない年にはリムーザンオークのみで造っています」。
リムーザンオーク樽は、フランスのコニャック地方で造られている高級ブランデー「コニャック」に使われる。メルローとの相性が非常によく、熟成に使うと独特の芳香が付与されるのが特徴だ。
「言葉で表すのは難しいのですが、樽ごとの仕上がりの違いは歴然です。『秩父 KARASAWA メルロ リムーザンオーク樽貯蔵』には、しっかりした味のチーズやペッパーを効かせたステーキなどを合わせてみてください」。
季節ごとのイベントや、特別なディナーを華やかに彩ってくれる1本だ。

▶︎「源作印 秩父 シャルドネ」
最後に紹介するのは、「源作印 秩父 シャルドネ」。自社畑のシャルドネを使った上質な辛口白ワインである。シャルドネのポテンシャルを余すところなく表現しており、香りの立ち方が非常に上品だ。
村田さんが当たり年だと語るのは、「源作印 秩父 シャルドネ」の2007年ヴィンテージ。エキス分が強く澱の量も特に多い。美味しさを余すところなく味わってもらうため、ワイナリーの直売所限定で無濾過の状態で販売している。熟成を経て酸がまろやかになり、コクが出て香りもより豊かになっているという。
「源作印 秩父 シャルドネ」に合わせて食べたい料理は、焼き牡蠣。さっと火を入れてバターを落とした牡蠣のクリーミな味わいに、シャルドネの風味が絶妙にマッチする。また、秩父の名産品である「杓子菜(しゃくしな)」の漬物を刻んでクリームチーズに混ぜたペーストを、野菜スティックにつけて食べるのもおすすめだ。秩父ならではの楽しみ方で、発酵食品同士の相性のよさを実感できるだろう。

『まとめ』
創業者の浅見氏が目指したのは、地元の人が郷土料理とともに気軽に飲むことができるワインを造ること。創業時から変わらぬ理念を受け継ぎ、秩父ワインはこれからも地元の人たちに愛されるワイン造りを続けていく。
「ワインというと敷居が高く感じられるかもしれませんが、家にあるおつまみと一緒に気軽に楽しめるような存在のワインを造っていきたいと思っています。ワインの力で、みなさんの生活がちょっと楽しいものになれば嬉しいですね」。
一方で、国内のワインコンクールで数々の賞を獲得している秩父ワインは、今後は海外への進出も視野に入れている。
「ブルゴーニュで開催された日本ワインの試飲イベントに、甲州のシュールリーやボルドー系の赤ワインなどを出品した経験があります。クラシカルな造りの赤ワインは現地でも好評でした。『源作印』という漢字が大きく描かれたエチケットも、インパクトが大きかったようですね」。
秩父ワインは清流や紅葉の名所、温泉など自然豊かで観光名所も多い場所にあり、東京から日帰りも可能だ。古きよき日本の懐かしい原風景が残るエリアに足を運んでリラックし、秩父ワインの美味しいワインを堪能する旅にふらりと出かけてみてはいかがだろうか。

基本情報
| 名称 | 秩父ワイン |
| 所在地 | 〒368-0201 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄41 |
| アクセス | ・秩父駅/西武秩父駅より バスにて45分「小鹿野車庫」下車徒歩12分 ・関越自動車道「花園IC」から45分 大型バス可の無料駐車場有(普通車約20台) |
| HP | https://chichibuwine.co.jp/ |