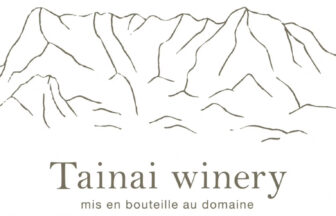鳥取県倉吉市の旧市街地には、「国重要伝統的建造物群保存地区」に選定されているエリアがある。赤瓦に白い漆喰壁の町屋が連なる、風情豊かな街並みだ。
今回紹介する「倉吉ワイナリー」は、そんな町屋をリノベーションした醸造所でワインを造っているワイナリーだ。1階には醸造施設があり、2階には地元食材とともに蔵出しワインが楽しめるワインカフェを併設。歴史を感じる空間にはシックな内装が施されており、心地よく過ごせる。
倉吉ワイナリーでぶどう栽培からワイン醸造までを手掛けるのは、「株式会社いまむらワイン&カンパニー」の代表取締役社長である今村憲治さん。ワイン造りを志し、2010年に京都府から倉吉に移り住んだ人物だ。今村さんは、ワインを通じて地域の魅力を発信し、訪れる人々に日本のワイン文化を知ってもらうことを大切にしている。
今回は今村さんに、ワインとの出会いと倉吉ワイナリー誕生の背景、ぶどう栽培とワイン醸造にかける思いについてお話いただいた。
『倉吉ワイナリーの発足まで』
まずは、倉吉ワイナリー設立までの物語を振り返ってみよう。学生時代からワインを飲んでいたという今村さんだが、自らぶどう栽培とワイン醸造を手がけるまでにはさまざまな紆余曲折があった。そもそも、どうして自らワインを造ろうという考えに至ったのだろうか。
「いつか自分で栽培したぶどうでワインを造ってみたいと考えたことはありましたが、当時は具体的な行動を起こしたわけではありませんでした。大学卒業後には別の業界の仕事に就きました。その頃に訪れたちょっとした出会いが、今思えば、ワイン造りを志したきっかけでしたね」。
▶︎アメリカで見た、ぶどう畑が広がる風景
30~40代にかけて、仕事の関係でアメリカ・オハイオ州で過ごした今村さん。あるときオハイオ州で土地が売りに出されている看板を目にした。「売地」の看板が立っていたのは、アーリー・アメリカン調の家付きの広大なぶどう畑だ。価格は東京でマンションを買うのよりも安いくらいだった。
「この土地を買って自分でぶどうを栽培して、ワインを造って暮らしたら面白いだろうなあと考えました。しかし実際には、当時のアメリカで日本人が土地を購入してぶどう栽培を始めるには予想以上に多くのハードルがあり、実現には至りませんでした」。
やがて50代になり、帰国の時を迎えた今村さん。自分の人生を振り返り、今までの人生は自分が本当にやりたいことをして来たのか?と自問自答したそうだ。これからやってみたいことはなんだろうと考えた際にふと脳裏に浮かんだのは、オハイオ州で見たぶどう畑だったという。
「この先の人生は、ぶどう栽培とワイン造りに明け暮れるのもよいのではと考えました。周りの人たちにはずいぶん反対されましたが、娘だけは賛成してくれました。今こうして夢を実現しましたが、大変なことも多いので、あの時みんなの意見を聞いておけばよかったと反省しているところです」と、今村さんはイタズラっぽく笑う。
▶︎理想の栽培地を求めて
ワイン醸造に使うぶどうの栽培敵地を検討した結果、鳥取県倉吉市でぶどう栽培をすることに決めた今村さん。
「北海道から九州まで、多くのワイナリーを訪ね歩いて話を聞きました。日本の気候は、みずみずしく美味しい生食用ぶどうの栽培には向いていますが、凝縮感があるワイン専用品種の栽培は難しいことがわかりました。暗渠を掘ったり排水対策したりと、みなさんいろいろと工夫していましたね」。
雨が多く湿度も高い日本で、ワイン専用品種の栽培を成功させるにはどうすればよいのか。例えば、フランスのボルドー地方のように、ぶどうの生育に理想的な環境を見つけるのは難しい。そこで、今村さんが注目したのが「砂地」だった。日本には砂地の土壌がいくつかあるが、最終的に鳥取県が最も適していると判断したのだ。
鳥取県は、西日本の最高峰「大山(だいせん)」を擁し、台風や豪雨の影響を受けにくい地域である。特徴的な土壌と共に、自然災害のリスクが少ないという点も大きな魅力だった。そして2010年、今村さんは鳥取県に移住することを決めた。

▶︎粘り強く信頼を築く
初めての土地で農業をスタートするのは予想していたよりも大変だったと、当時を振り返る今村さん。畑を貸してくれる人がなかなか現れなかったのだという。余所者に自分の土地を貸すのに抵抗があるのは当然のことかもしれない。京都出身の今村さんにとって、鳥取は親戚も友人もいない土地だった。
そこで今村さんは、地域のさまざまな会合に積極的に顔を出して、コミュニケーションをとることを心がけた。お酒の席では一緒にワインを飲んで、ぶどう栽培とワイン造りにかける熱い思いを伝えたのだ。
「実は、鳥取は生食用ぶどうの産地なのです。砂地は農業が難しいため、明治頃からは乾燥に強いぶどう栽培がおこなわれてきました。また、日本酒と焼酎が好まれる土地柄とはいえ、ワインを好む人は鳥取にもわりといるのです。人間関係を構築して徐々に地域に溶け込んでいきました」。
努力の甲斐あって、今村さんの活動を応援してくれる人がだんだんと増えてきた。努力の甲斐あって、移住から約1年経った頃には、畑を使ってもよいという人が現れ始めた。ようやく鳥取でのぶどう栽培をスタートさせることができたのだ。

『倉吉ワイナリーのぶどう栽培』
続いては、倉吉ワイナリーのぶどう栽培にスポットを当てていこう。倉吉ワイナリーの自社畑は、倉吉市に隣接する鳥取県東伯郡(とうはくぐん)北栄町(ほくえいちょう)にある。日本海沿いに広がる「北条砂丘」にほど近く水はけがよい砂地で、ぶどう栽培をおこなっているのだ。
鳥取県でのぶどう栽培の様子と土壌の特徴、自社畑周辺の気候について確認していきたい。また、栽培している品種や栽培管理におけるこだわりについても尋ねてみた。
▶︎倉吉ワイナリーの自社畑
倉吉ワイナリーの自社畑は、日本海から100mほど内陸に入った場所にある。砂地で水はけがよいのが特徴だ。海から常に吹きつけてくる風が湿気を吹き飛ばし、ワインにミネラル分をもたらしてくれる。また、朝晩の寒暖差も大きいため、ぶどうの糖度が高くなりやすいという。
また、北栄町でぶどう栽培をする上で特にメリットなのは、夏場の日照時間が長く、雨が少ないところだという。
自社畑では垣根栽培を採用し、ヨーロッパ系品種のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルロー、シャルドネを栽培。さらに、ヤマソービニヨン、マスカット・ベーリーA、ハニービーナスなども植栽している。毎年少しずつ圃場を拡大しているため、最も最近植えたものはまだ4年目の若木だ。
「特に土地に合うと感じているのは、メルローとヤマソービニヨンですね。カベルネ・ソーヴィニヨンやシャルドネなどは雨の影響を受けやすい品種のため、雨よけのビニールを設置しています。大山がさえぎってくれるおかげで台風被害を受けにくい土地なので、助かっています」。

▶︎栽培管理における工夫
栽培管理においてこだわっているのは、安全性の高いぶどうを作ることだ。自社畑で栽培しているぶどうには、化学肥料や除草剤を一切使用していない。また、防除の回数も最小限に抑えているという。
「薬剤で真っ白になったぶどうでワインを造るようなことは避けたいと思っています。日本の気候では薬剤を使わないぶどう栽培は非常に難しいですが、できるだけ安全性を担保できるものだけを作るようにしています。総面積1.5haという小規模だからこそ実現できる栽培方法ですね」。
ワイン造りにおいて何よりも大切なのは、ぶどうの質だと断言する今村さん。よいワインを造るには、よいぶどうが必要不可欠だ。ワイン醸造に携わって10年以上経つが、収穫は毎年異なり、生まれるワインもまた違ってくる。毎年異なるぶどうの個性に向き合いながら、理想のワインを追求し続けているのだ。

『倉吉ワイナリーのワイン醸造』
50歳までワイン造りとは全く異なる職業に従事していた今村さんは、ワイナリー設立を決意してから、広島県東広島市にある「独立行政法人 酒類総合研究所」での講習を受講。また、何軒ものワイナリーに住み込んでぶどう栽培とワイン醸造に関する実践的な知識を付け、経験を積んできた。
今村さんの願いは、「美味しいワインを造ること」。価格やブランドでよしあしを判断するのではなく、飲んだ人が素直に「美味しい!」と思えるワインを目指している。倉吉ワイナリーのワイン醸造に迫っていこう。
▶︎クリーンな風味のワイン
樽を使わない醸造をおこなっている倉吉ワイナリー。6か月間ステンレスタンクで熟成させた後、瓶に詰めて3~4か月置いてさらに熟成させる。ぶどう本来の味わいをダイレクトに引き出した、品種特性が感じられる味わいが特徴だ。
一般的には瓶詰め前に実施することが多いという、フィルターを使用したろ過もおこなっていない。代わりに、「澱(おり)引き」と呼ばれる工程を3回ほど繰り返し、タンクの中で自然に澱を落としながらワインを熟成させている。
「フィルターでろ過すると綺麗な見た目のワインになりますが、同時に果実味も取られてしまいます。ろ過をあえてしないことで果実味がしっかり残り、ぶどうを口に含んで噛んだ時のような果実感や、果皮の渋みといった味わいまで感じられるワインができるのです」。

▶︎グラビティを生かした醸造
倉吉ワイナリーでは、「グラビティ(重力)」を生かしたワイン造りにもこだわっている。醸造工程の中でワインを移動させる際にポンプなどの機械を使わず、重力で液体を自然に移動させる「グラビティ・フロー」と呼ばれる手法を採用しているのだ。
ワインをタンクに入れる際に3名がかりでバケツリレーをする作業は、かなりの重労働。だが、より優れた品質の美味しいワインを造るためには欠かせない工程だという。
これまで自社醸造をしてきた中で、何度も失敗を経験してきたと話してくれた今村さん。ワイナリー設立当初には、仕込んだ甲州がなかなか発酵せず、タンクを電気毛布で包んであたためてなんとか発酵させることに成功させた経験などを振り返る。
「小さな失敗は今でもたくさんありますが、原因を突き止めてやり直す過程も興味深く楽しいものです。ワイン造りは、誰にやれと言われたわけでもなく、やりたくてやっていることですからね。やりたいことがなかなか見つけられない人も多い中で、自分が心からやりたいと思えることに出会えたことは、本当に幸せなことだと思っています。見つけられたことに感謝ですね」。
造り手が苦労をものともせず、楽しみながら造っているワインには、造りながら感じたさまざまな思いが深く表現されているに違いない。

▶︎「カンパニー」のメンバーと共に取り組む
倉吉ワイナリーには、「IWC(いまむらワイン&カンパニー)サポート倶楽部」という組織がある。サポート倶楽部は倉吉ワイナリーのぶどう栽培とワイン造りをサポートするメンバー「カンパニー」で構成されており、今村さんやワイナリーのスタッフと共に栽培や醸造に携わっているのだ。
春先や収穫の時期など、通常よりも多くの人手が必要な時期には、2名の専属スタッフだけでなく、「カンパニー」のメンバーと協力してワイン造りをおこなっているそうだ。
「カンパニー」という言葉は、日本語では一般的に「会社」という意味で使われる。しかしもともと英語の「Company」には「仲間」という意味合いが強いことから名付けられた組織名だという。仲間と共に協力しながらワイン造りに取り組むのが、倉吉ワイナリー流の進め方なのだ。
カンパニーのメンバーの中にはぶどう農家もいるため、栽培したぶどうを倉吉ワイナリーが買い取ることもある。ワイン原料用のぶどうを売買する際にはkg単位で価格を決めて取引するのが一般的だが、倉吉ワイナリーでは、栽培者もワイン造りに参加して売上を折半する方法を採用しているという。
「買い上げ価格が安いと、どうしても質より量という考えになってしまいがちです。試行錯誤して、農家によいぶどうを作ってもらうための取り組みとして始めました。農家さんにもワインができて売れた時の喜びを感じてもらうことが、もっと美味しいぶどうを栽培することに繋がり、よい循環を生み出すでしょう。

▶︎ミネラル感あふれる「伯州 シャルドネ2023」
ここで、今村さんおすすめの銘柄をふたつ紹介しよう。鳥取県には海の恵みも山の恵みも豊かなため、それぞれの食材に合うワインを楽しんでほしいそうだ。海の食材ならシャルドネ、肉系ならメルローをペアリングしたい。
「伯州 シャルドネ2023」は、柑橘系の果実味と酸味、ミネラル感が特徴。ぶどう畑に吹き込む潮風の影響でミネラル分を多く含んだぶどうならではの味わいが感じられる辛口ワインで、「潮の香りがする」という感想も聞かれるそうだ。
魚介類を使った和食との相性が抜群で、特に鳥取の名物である岩牡蠣とのペアリングが一押し。鳥取の岩牡蠣は大きく甘みがあり「伯州 シャルドネ2023」との相性抜群だ。また、酸味があるシメサバやサバ寿司と合わせるのも美味しい。

▶︎果実味豊かな「実結(みゆ) メルロー」
続いては、果実味が存分に感じられる赤ワインの「実結(みゆ) メルロー」。自社畑で栽培したメルローとヤマソーヴィニヨンを使用し、6か月間ステンレスタンクで発酵させた。清澄剤を使用せずに瓶詰めした、しなやかなタンニンと程よい酸味が特徴だ。樽を使用していないため、メルローそのものの味わいが引き立つ仕上がりとなっている。
「実結(みゆ) メルロー」にペアリングする料理として今村さんがおすすめしてくれたのは、「クレソンの鴨鍋」である。ある小説に登場する料理を参考にして、今村さん自らが考案したメニューなのだとか。
冬季限定だが、事前に予約しておけばワイナリー2階のワインカフェでワインと一緒に楽しむことができる。倉吉市・関金(せきがね)のわさび畑に自生しているものを朝穫りした新鮮なクレソンを使用しているそうだ。
「ワインカフェはテイスティングルームとして使用していますが、予約いただければ料理も提供しています。築150年の指定伝統建築物で、美味しい料理とワインを味わうゆったりとした時間をお過ごしください」。
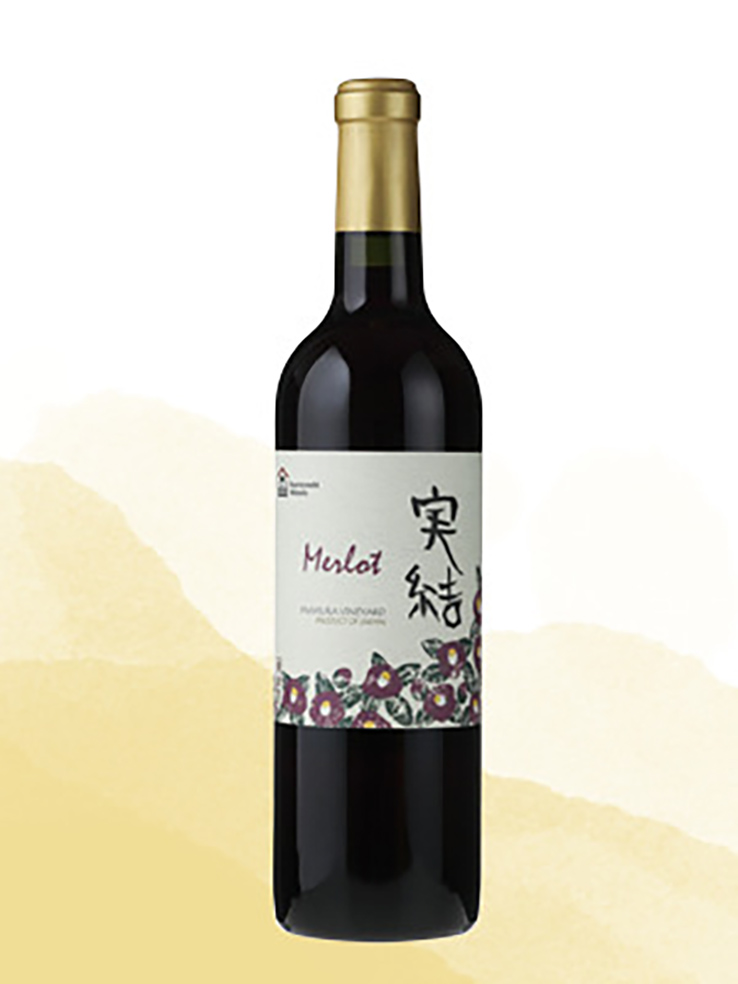
『倉吉ワイナリーのさまざまな取り組み』
鳥取県倉吉市の旧市街地には、築150年を超える歴史的な白壁土蔵の建物が数多く残っている。かつては商家や造り酒屋、醤油屋が建ち並んで賑わっていた。今村さんは、なぜ倉吉ワイナリーに歴史ある建造物を利用したのだろうか。
「当初は、一般的なワイナリーと同じようにぶどう畑の横に新しい建物を建ててワインを造ることを考えていました。しかし、変わったことをしたがる、私のへそ曲がりな性格が出てしまったのです。そこで歴史的な風貌の建物を生かして、新しい形のワイナリーを作ることにしました」と、豪快に笑う今村さん。
こうして生まれたのが、伝統的な風情を取り入れた造り酒屋風のワイナリーだ。同じ通り沿いには日本酒蔵やクラフトビール、ウイスキーなどの醸造所もある。お酒好きにはたまらないスポットだ。
▶︎新たな挑戦にも意欲的
倉吉市の旧市街地に軒を連ねるワイナリーとして、街ぐるみでのイベントにも積極的に参加している倉吉ワイナリー。商店街全体で共通利用可能な商品券の発行や、飲み歩きイベントの開催など、地域活性化に取り組んでいる。
「挑戦してみたいことはたくさんありますね。小規模だからこそ、いろいろなチャレンジができるということが倉吉ワイナリーの強みです」。
醸造においては、現在ステンレスタンクを使った醸造がメインではあるものの、将来的には樽を使ったワインを造って、長期熟成にも取り組んでみたいと考えている。そのためには、ぶどう作りにおいても醸造においても、さらに技術や知識を磨いていく必要があると話してくれた。
▶︎体験プログラムも企画中
倉吉ワイナリーでは、さまざまなイベントを構想している。主に都市部の人をターゲットとした、ワイン造りを身近に感じられる体験ツアーもそのひとつだ。参加者には春から秋にかけて定期的に現地に足を運んでもらい、収穫から仕込みまでの工程を体験する。ワイナリーの近隣には宿泊施設もあるため、泊まり込みのプログラムも可能だ。3日間程のプログラムを通して、参加者にワイン造りの魅力を伝えていくことが目的だという。
「ワインが好きな方でも、ぶどう畑や醸造の様子を見たことがないという方はたくさんいると思います。ワイン造りを体験して、ワインをより身近に感じれいただければ嬉しいですね」。

『まとめ』
飲んだ時に、『これぞワイン』と思ってもらえる美味しいワインを造りたいと考えている今村さん。言うのは簡単だが、実現するのは非常に難しい。
「10年以上もの間ワイン造りに取り組んでいても、理想に近い仕上がりになることは稀ですね。2018年と2020年のメルローは素晴らしかったのですが、実はいまだに、私自身が心から満足するワインはできていないのです。ぶどうがよければ美味しいワインができると信じているので、これからも高品質なぶどうを造るために努力していきます」。
2024年は栽培だけでなく、収穫のタイミングにもこだわった。倉吉ワイナリーでは、以前は収穫祭を開催してカンパニーメンバーと共に1日で収穫を終わらせていた。だが、植栽している区画によって成長の差が生まれることもある。同じタイミングで全てを収穫すると、早すぎたり遅すぎたりしてしまうことも多かったのだ。
「同じ畑でも、列によって熟度が違うことなどもよくあります。スタッフから収穫するタイミングを変更する提案を受けたので、2024年は2回に分けて収穫してみました。今後も高品質なぶどうを栽培するために、試行錯誤を重ねていきます」。
今村さんの願いは、日本人の食生活やライフスタイルにワインをより浸透させていくことだ。海外にも美味しいワインはたくさんあるが、日本ワインにもぜひ親しんでもらいたいと考えている。
日本ワインを「より日常的なもの」として生活に取り入れる機会を増やしたい。そんな思いで倉吉ワイナリーがおこなっているさまざまな取り組みを、引き続き応援していきたい。

基本情報
| 名称 | 倉吉ワイナリー |
| 所在地 | 〒682-0825 鳥取県倉吉市西仲町2627 |
| アクセス | 倉吉ワイナリーアクセス |
| HP | https://www.kurayoshi-winery.com/ |